習い事は何歳からはじめた方がいい?年齢ごとのおすすめの習い事

子どもが興味を持ちはじめるタイミングで「習い事」を検討する保護者は多いでしょう。しかし「いったい何歳からはじめればいいの?」「どんなジャンルが向いているの?」と迷うことも少なくありません。
幼児期から小学生、中学生にかけて、成長段階にあわせた適切な習い事を選ぶことで、子どもの可能性を大きく伸ばせるかもしれません。そこで本記事では、年齢別のおすすめ習い事や、はじめるときのポイントなどを紹介していきます。
記事まとめ
- 「習い事を何歳からはじめるべきか」は子どもの発達速度や性格、家庭環境によって大きく変わる。
- 習い事は、子どもの性格や好みを見極めつつ、体験レッスンや見学を利用した上で、スケジュールと家計を考慮して選ぶことが大事。
- 夕方以降や夜間の習い事は防犯面が心配であるため、必要に応じて大人の送迎や、キッズケータイの活用であんぜんを確保するとよい。
習い事は何歳からはじめたらいいの?
習い事をはじめたきっかけは?
子どもが習い事をはじめるきっかけはさまざまです。なかでも、下記のような理由で検討する保護者が多いようです。
1.子どもの興味や才能を伸ばしたい
・子どもが音楽やスポーツに強い関心を示すので、専門的に学ばせたい。
・将来に役立つ技能を幼いうちから身につけてほしい。
2.コミュニケーション能力の向上
・ほかの子どもたちと活動をともにすることで、協調性や社交性を育てたい。
3.体力・健康面の強化
・運動不足を解消したい。
・免疫力や身体能力を高めるためのスポーツ系習い事を希望する。
4.集中力や表現力を身につけたい
・学習系の習い事で学習習慣を付けたい。
・音楽やアートで自己表現を楽しめるようになってほしい。
一方、「習い事を何歳からはじめるべきか」は子どもの発達速度や性格、家庭環境によって大きく変わります。
早ければ0歳から参加できる教室もあれば、小学生以降に本格的にはじめるのが適している習い事もあります。習い事のはじめどきは、子どもの興味や意欲を見極めることも大切です。
習い事に1人で行けるのは何歳から?

保護者の送迎が必須かどうかは、習い事の場所や時間帯にも左右されますが、一般的にいわれるのは以下の目安です。
・未就学児~小学校低学年:保護者が基本的に送迎する。
・小学校中学年~高学年:あんぜんな通学路や交通手段が確保されれば、一人で行かせるケースが増える。
・中学生以上:部活動や自立度が高まり、習い事に一人で通うことがほとんどになる。
とはいえ、夕方以降や夜間の習い事は防犯面が心配です。必要に応じて大人の送迎や、キッズケータイの活用であんぜんを確保するとよいでしょう。
送迎の負担軽減!オンラインでの習い事
近年はオンラインで学べる習い事も増えています。ピアノやダンスなど実技系のハードルはやや高いものの、英会話やプログラミング、学習塾などはオンライン対応が進んでおり、自宅で受講できるのが大きなメリットです。
送迎の負担が軽減され、スケジュールも組みやすいため、忙しい保護者にはうれしい選択肢といえるでしょう。
【年齢別】はじめやすいおすすめの習い事

子どもの成長段階に応じて、向いている習い事の種類やアプローチは異なります。以下では、0~2歳、3~6歳、小学生、そして全年齢ではじめやすい習い事をまとめました。
【0~2歳からはじめる】おすすめの習い事
・ベビースイミング
・水に慣れることで将来的な水泳の習得がスムーズになる。
・親子で一緒に参加し、スキンシップを深められる。
・リトミック
・音楽に合わせて体を動かし、リズム感や感性をはぐくむ。
・親子で楽しめるプログラムが多い。
・ベビーマッサージ教室
・厳密には「習い事」というよりは親と子のコミュニケーション講座に近い。
・触れ合いを通じて子どもの情緒を安定させる。
この年代は「習い事」というより、親子の交流や感覚刺激がメインです。子どもの発達を促すと同時に、保護者同士の情報交換の場にもなります。
【3~6歳からはじめる】おすすめの習い事
・スイミング
・体力や心肺機能を向上させるとともに、早期から水に慣れるメリットが大きい。
・基礎的な泳ぎ方を学ぶことで、水への恐怖心がなくなる。
・体操教室
・柔軟性やバランス感覚、運動能力全般を伸ばす。
・マット運動や跳び箱など、楽しみながら基本動作を身につけられる。
・音楽教室(ピアノ、リトミック)
・音感やリズム感、集中力を養う。
・グループレッスンの場合、ほかの子どもとの協調性を学べる。
3〜6歳は幼稚園・保育園での生活にも慣れはじめる年齢です。子どもの興味を尊重しつつ、体を動かす習い事や音楽を楽しむ習い事などにチャレンジさせるとよいでしょう。
【小学生からはじめる】おすすめの習い事
・サッカー・野球・バスケなどの球技
・チームワークやコミュニケーション能力をはぐくむ。
・試合を通じて達成感や協調性を学ぶ機会が増える。
・英会話
・グローバル化の時代、英語への抵抗感がなくなるのは大きなメリットです。
・小学生から本格的に学べば、中学以降の英語学習がスムーズになる。
・書道・そろばん
・集中力や美しい字形、正確な計算力など基礎的なスキルを習得する。
・比較的月謝が安く、継続しやすい。
小学生になると、友達との比較や本人の意欲が高まる一方で、学業や塾、部活動などとのスケジュール調整もポイントです。子どもにとって無理のないペースで続けられるかを考えましょう。
【全年齢ではじめる】おすすめの習い事
・学習塾(進学塾)
・学年や目的に応じて選ぶことで、基礎学力や受験対策に役立つ。
・学年が上がるほど専門的なコースがある。
・音楽系(ピアノ、バイオリン、ギターなど)
・年齢問わずはじめられるが、早期から触れるとリズム感や音感が定着しやすい。
・個人レッスンやグループレッスンなどスタイルを選びやすい。
・そろばん・公文式
・幼児期から高校生まで幅広い年齢で学べる。
・計算力や学習習慣を身につける目的で長期的に通う家庭も多い。
どの年齢でも興味さえあればはじめられる習い事がある一方で、「あのとき早くはじめておけばよかった」と思うこともあるかもしれません。
子どもの意欲を見極め、いつでもはじめられるという柔軟な姿勢をもつとよいでしょう。
はじめての習い事を選ぶポイント
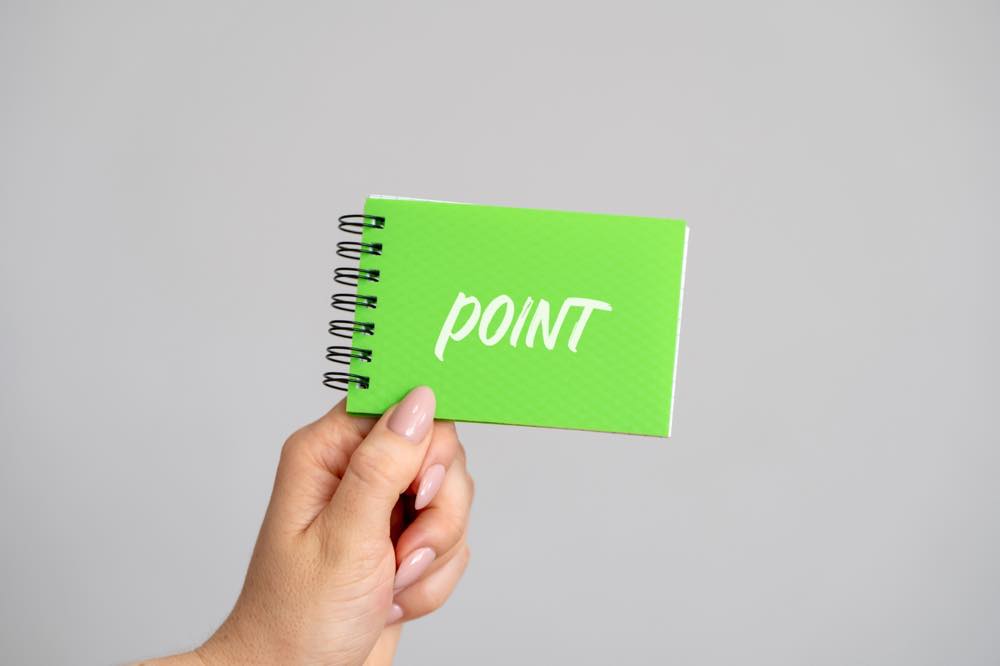
はじめての習い事を選ぶ際は、子どもが楽しく続けられる、かつ親としても無理なく通わせられるものを選ぶことが大切です。ここでは、選ぶ際のポイントを3点ご紹介します。
1.子どもの性格や好みを見極める
・活発に動き回る子にはスポーツ系、じっくり作業するのが得意な子にはアート系などを選ぶ。
・本人の興味を尊重することで、長続きしやすい。
2.体験レッスンや見学を利用する
・初心者向けの無料体験や見学会に参加し、子どもが楽しめるか確認する。
・講師や教室の雰囲気をしっかりチェックする。
3.スケジュールと家計を考慮する
・週に何回通う必要があるのか、送迎は必要か、月謝や教材費などの費用感も重要です。
・複数の習い事を同時に検討する場合、無理のない組合わせを探す。
習い事をはじめたら保護者の方が気をつける事
子どもが習い事をスタートした後も、保護者として気を配るべきポイントがあります。ここでは4点ポイントをご紹介します。子どもが楽しく続けられる環境づくりをサポートしましょう。
1.適度な距離感を保つ
・親が干渉しすぎると、子どもが自主性を失いやすいです。
・成長を見守りつつ、必要なときにアドバイスする程度が理想です。
2.成果だけでなく過程を褒める
・結果にこだわりすぎると、子どもは失敗を恐れたり嫌気が差したりするので注意しましょう。
・小さな成長や努力を見逃さず、具体的にほめることが大切です。
3.送迎や防犯面を考慮する
・夜遅くなる習い事や遠方の場合、防犯リスクが高くなります。
・防犯対策として、キッズケータイやGPS機能付きスマホなどで行き帰りのあんぜんを確保しましょう。
4.親子のスケジュールを定期的に見直す
・子どもが成長するにつれ、習い事へのモチベーションや難易度も変化します。
・学校行事や部活との兼ね合い、家計とのバランスを定期的にチェックしましょう。
子どもの可能性を最大限に伸ばすためには、適度なサポートと本人の意欲を尊重することが欠かせません。
楽しむ姿を見守りつつ、親子で協力して習い事ライフを充実させていきましょう。
NTTドコモのキッズケータイ

習い事の場所や時間帯によっては、お子さまが一人で行き帰りをしなければならない場面が出てきます。特に暗くなる時間帯や人通りが少ない道を通る場合、防犯面が気になるという保護者の方も多いでしょう。
そこで習い事の行き帰りの防犯に検討したいのがキッズケータイです。
NTTドコモのキッズケータイでは、家族などのあらかじめ登録した相手とのみ、通話や「+メッセージ」でのやりとりが可能です。また、いざというときの防犯ブザー機能など、親子にうれしい機能が充実しています。
詳細は、下記よりご覧ください。
https://comotto.docomo.ne.jp/kidskeitai
まとめ
「習い事は何歳からはじめたらいい?」という問いに、明確な正解はありません。しかし、子どもの成長段階や性格、興味に合わせて習い事を選べば、より充実した時間を過ごせる可能性が高まります。
さらに、習い事をスタートさせたら、送迎や費用、子どものペースなどに気を配り、親子で無理なく取組めることが大切です。
オンラインレッスンを活用したり、行き帰りの連絡手段としてキッズケータイを活用するなど、現代ならではの方法も取入れながら、子どもが楽しみながら成長できるように、親子で相談しながら最適な習い事を見つけてください。
