入学祝いはいつ渡す?タイミングや誰に渡すべきかのまとめ

お子さまやお孫さん、姪や甥といった親戚や知人のお子さんが、幼稚園や小学校、中学・高校、大学などへ進学するタイミングに合わせて贈る「入学祝い」。春が近づくと、「そろそろ入学祝いを用意しないと」と考える方が増えてきます。
しかし、実際には「いつ頃渡せばいいの?」「誰に贈るべき?」と、タイミングや相手の範囲について迷うことも少なくありません。
そこで本記事では、入学祝いを贈る上で知っておきたい「贈る時期や相手」「贈りそびれた場合の対応」など、基本的なポイントをまとめました。
記事まとめ
- 入学祝いは、一般的には3月初旬から中旬にかけて渡すのがベストタイミングだといわれている。
- 贈るべき相手の範囲に明確な決まりはありませんが、あまり親しくない場合や義理で贈る場合は、相手に気を遣わせる可能性もあるので注意しましょう。
- 喪中であっても、身内の慶事を祝うこと自体はマナー違反ではないといわれていますが、四十九日が明けてから贈るなどの配慮が大切になる。
入学祝いはいつ贈ればいい?

まずは、入学祝いを贈る時期について確認していきましょう。入学式は4月初旬に行われるケースが大半ですが、準備が必要な家庭にとっては「お祝いの使い道」を早めに考えたいところです。それに合わせて、できるだけスケジュールに余裕を持って渡したいものです。
3月初旬から中旬が一番適切
一般的には、3月初旬から中旬にかけて渡すのがベストタイミングだといわれています。なぜなら、多くの学校が3月下旬に卒業式、そして4月上旬に入学式をむかえるからです。子どもの新生活に向けた入学準備(制服や教材の購入など)は、3月後半から本格化するため、その前にお祝いを贈っておけば、必要な費用として役立ててもらえます。
もし、学校の合格発表が2月下旬~3月上旬に行われる場合は、合格が確定したあたりのタイミングを目安に準備を進めるといいでしょう。相手も「合格かどうかわからない時点で大きな出費をするのは不安…」と感じているかもしれませんから、早めにお祝いが届くと助かるケースも多いです。
姪や甥にはいつ贈る?
姪や甥への入学祝いも、基本的には3月初旬〜中旬が理想的です。両親(あなたのきょうだい)の予定を確認し、相手が忙しくない日や帰省のタイミングなどを考慮してスケジュールを立てるとスムーズです。
甥や姪の場合は、子ども本人と顔を合わせる機会が限られることもあります。可能であれば、直接会って手渡しできる日程を調整し、それが難しければ郵送や宅配便を活用するのもうよいでしょう。
受験の場合は合否が判明してから贈る
中学校、高校、大学など、受験の合否がある場合は、合格通知が届いてから贈るようにしましょう。受験結果がまだ分からない段階でお祝いを贈ると、「万が一不合格だったらどうするの?」と相手に気を遣わせる可能性があります。場合によっては失礼だと捉えられることもあるため、注意が必要です。
ただし、合格発表が遅め(3月中旬〜下旬)の学校もあるため、結果が分かったらなるべく早めにお祝いを渡せるよう、あらかじめ準備だけは整えておくのがおすすめです。
入学祝いは誰に贈ればいい?

入学祝いは、基本的には身内や親しい知人・友人のお子さんに贈るのが一般的です。具体的には、以下のような相手が対象となります。
・孫(祖父母から)
・甥・姪(叔父・叔母から)
・いとこや親戚の子ども
・親しい友人の子ども
・地域の習慣によっては、近所や知り合いの子ども
贈るべき相手の範囲に明確な決まりはありませんが、あまり親しくない場合や義理で贈る場合は、相手に気を遣わせる可能性もあるので注意しましょう。
逆に、親密な関係でありながら「お祝いを贈り忘れた」なんてことになると、少し気まずさが残るかもしれません。自分の家族や親族、友人たちの状況を把握し、必要に応じてお祝いの用意をしておくとあんしんです。
入学祝いを贈れなかったらいつまでに贈る?
もし何らかの事情で3月中旬に間に合わず、渡しそびれてしまった場合は、遅くとも入学式が行われる4月上旬までには渡すよう努めましょう。入学式前後は、子どもの新生活に必要な出費がかさむ時期でもありますから、少し遅れてもうれしく感じてもらえるはずです。
万が一、4月を過ぎてしまう場合でも、早めに連絡をして「お祝いを用意しているのですが、遅くなってごめんなさい」とひと声かけてから贈るとよいでしょう。感謝の気持ちをきちんと伝え、なるべく速やかに渡せば、失礼にはあたりません。
喪中の場合はいつ贈る?
喪中の場合でも、子どもの入学はおめでたいことに変わりありません。とはいえ、喪中という状況でお祝いをするのは失礼にならないか、と気にする方も多いでしょう。結論としては、喪中であっても、身内の慶事を祝うこと自体はマナー違反ではないといわれています。ただし、以下のような配慮が大切です。
■四十九日が明けてから贈る
可能であれば、故人の四十九日が過ぎて落ち着いた頃に渡すのが望ましいです。
■派手な包装や水引を控える
喪中であれば、簡易的なのし袋や控えめなデザインを選ぶとよいでしょう。
相手側が喪中であっても、入学式という一生に一度の行事であるため、お祝い自体は問題ありません。ただし、過度に華やかすぎない形で贈るのが無難です。
状況によっては相手との相談が必要なケースもあるため、やりとりを疎かにせず、相手の気持ちやタイミングをしっかり確認しましょう。
入学祝いはどうやって贈る?
入学祝いの贈り方には、大きく分けて手渡しと郵送(宅配便)の2種類があります。どちらを選ぶかは、距離やスケジュール、相手の都合などに応じて判断しましょう。
手渡し場合の送り方
直接会って渡すのが最も一般的で、相手とのコミュニケーションを取りやすい利点があります。子どもの表情を見ながら渡せば、お祝いする側も「成長したね!」などと声をかけやすいでしょう。
もし会うタイミングがなかなか取れない場合は、事前に連絡をして都合を合わせる工夫が必要です。
郵送の場合の送り方
遠方に住んでいたり、スケジュールが合わない場合は、郵送や宅配便で送る方法があります。
のし袋を用いて現金や商品券を送りたいときには、現金書留や宅配便の代金引換(ギフト券の場合)など、安全な方法を選びましょう。
送る際には、同封する手紙やメッセージカードに感謝やお祝いの言葉を添えることが大切。事前に「○日に届く予定です」と連絡をしておくとスムーズです。
卒業祝いと入学祝いをまとめる場合はどうすればいい?

子どもが卒業から入学までの期間が短いことから、「卒業祝いと入学祝いを一緒に贈りたい」と考える方もいます。特に中学・高校や高校・大学といった繋がりのある進学だと、わざわざ別々のタイミングで贈るよりもまとめて渡したほうが効率的だと感じるかもしれません。
結論としては、卒業祝いと入学祝いをまとめて贈ること自体は問題ありません。ただし、以下のようなポイントを押さえるとスムーズです。
相手に一言伝える
「卒業も入学もおめでとう。両方のお祝いとして贈りますね」と、きちんと伝えておきましょう。相手が混乱しないように、メッセージカードにも記載しておくとよいでしょう。
のし袋の表書き
「御祝」「祝卒業・入学」など、まとめて表記してかまいません。文面で「○○卒業と○○入学を一度にお祝いします」というニュアンスを伝えると、相手も受け取りやすいです。
金額はやや高めを意識する
まとめて贈るのであれば、単純に通常の2倍という必要はありませんが、少し多めに用意するとよいでしょう。相手が何かと物入りな時期なので、助かるケースが多いです。
また、卒業祝いと入学祝いを別々にきちんと渡すのが慣習となっている地域や家庭もあるため、無理にまとめる必要がない場合は、それぞれのタイミングで贈るのが一番スムーズかもしれません。どちらが適切か、家族や親族とのコミュニケーションを図りながら決めてみてください。
NTTドコモのキッズケータイ

小学生になると、お子さまの小学校の通学や習い事など、お子さまが一人で行き帰りをしなければならない場面が増えていきます。特に暗くなる時間帯や人通りが少ない道を通る場合、防犯面が気になるという方も多いでしょう。
そういった方に、小学校の合格入学祝いとしておすすめなのがキッズケータイです。
NTTドコモのキッズケータイでは、家族などのあらかじめ登録した相手とのみ、通話や「+メッセージ」でのやりとりが可能です。また、いざというときの防犯ブザー機能など、親子にうれしい機能が充実しています。
詳細は、下記よりご覧ください。
https://comotto.docomo.ne.jp/kidskeitai
U15はじめてスマホプラン
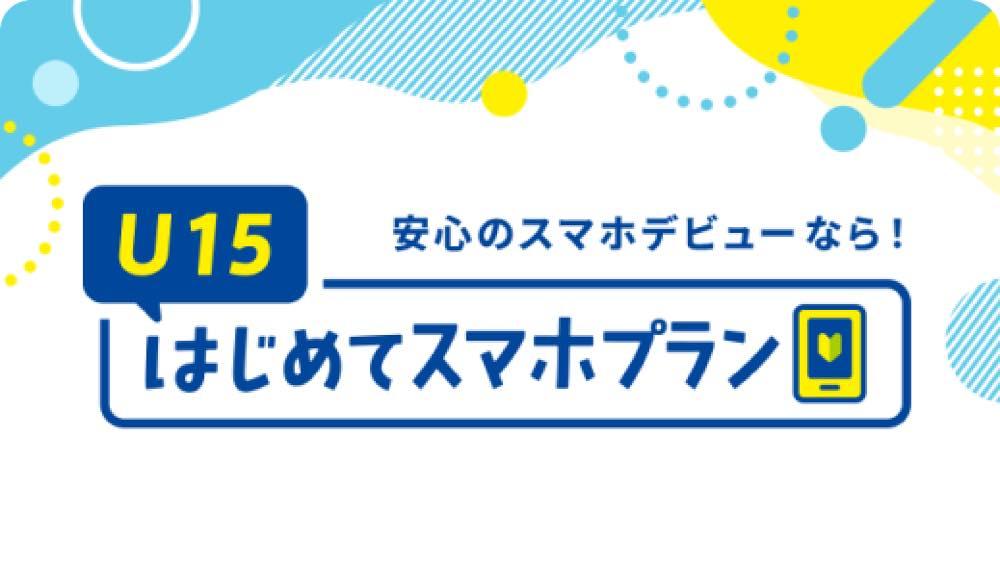
中学、高校の合格祝いとして、お子さまに持たせるはじめてのスマホはいかがでしょうか。
U15はじめてスマホプランとは、15歳以下のお子さまにあんしん、かつおトクにスマホデビューしていただけるプランです。使いすぎや有害サイトへのアクセスに対応できるフィルタリング機能や、危険サイトやウイルスなどの脅威からお守りするセキュリティサービスを提供し、親子で安心してスマートフォンを利用できます。
プランや料金に関する詳細は、下記よりご覧ください。
https://comotto.docomo.ne.jp/u15_hajimete_plan
まとめ
入学祝いを贈るタイミングや贈り先、卒業祝いとの兼ね合いなど、意外と迷いがちなポイントは多いものです。ですが、基本的には「相手の子どもがスムーズに入学準備できるよう、3月初旬〜中旬に贈る」という考え方をベースにすれば、大きな問題はありません。
そしてなにより、子どもにとっての入学は、大きな期待と少しの不安が入り混じる新生活のスタートです。お祝いを贈るときには、「おめでとう!これからも応援しているよ」といった素直な気持ちをしっかり伝えることが大切です。形だけでなく、言葉や気遣いも添えて、子どもの新たなステージを温かくサポートしてあげましょう。

スマホ・キッズケータイ
