子どもを「甘やかす」と「甘えさせる」の違いとは?甘やかすことによる悪影響もご紹介
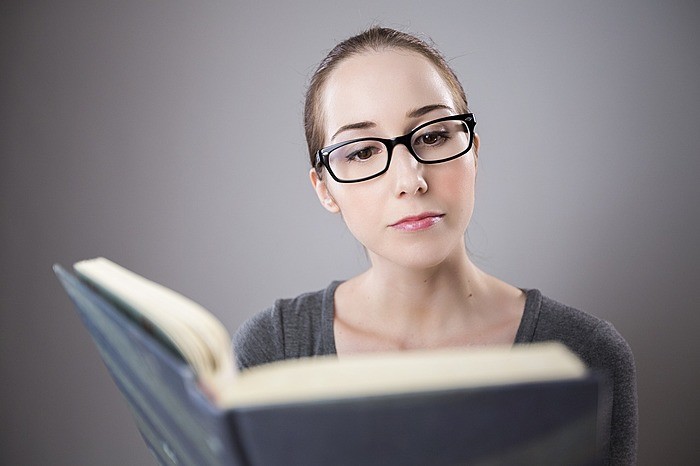
「甘やかす」と「甘えさせる」の差は何だろうと疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、「甘やかす」「甘えさせる」の意味の違い、子どもに対して「甘やかす」ことで悪い影響をおよぼすことなどを紹介します。子どもの教育で悩む方は参考にしてください。
「甘やかすと甘えさせるって意味は違うの?」
「ついつい甘やかしてしまっているけど、子どもの性格や将来に影響するの?」
「子どもを甘えさせてあげるとなにかいいことがある?」
このように、子どもの甘えについて不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「甘やかす」と「甘えさせる」では意味が変わってくる点や、「甘やかす」方に偏ると悪い影響がおよぶこと「甘えさせる」ことの重要さなどについて紹介します。
この記事を読むことで、子どもが甘えてくることの意味もわかり、自立心を伸ばす方法もわかってくるでしょう。子どもが甘えん坊で困っている方、子どもとの接し方に悩んでいる方などはぜひ、参考にしてください。
「甘やかす」と「甘えさせる」の違い
「甘やかす」と「甘えさせる」の意味は異なります。
「甘やかす」とは、子どもの要求に大人の都合で過剰に要求に応える、要求されていないのに子どもの世話をしてしまうことをさします。
一方、「甘えさせる」とは、子どもがなにかを要求した際に、それに応えることです。子どもの自主性を尊重し、要求があったときのみ、かかわる姿勢ともいえるでしょう。
「甘やかす」と「甘えさせる」の違いを詳しく紹介します。違いを把握しておきましょう。
「甘やかす」は子どもの物理的や金銭的な欲求を満たすこと
子どもの物理的や金銭的な要求に過剰に応じ、親が過保護な行動をとることを、「甘やかす」といいます。
たとえば、子どもがおもちゃを欲しがれば、すぐに買い与える、学校の準備や宿題などに対して、子どもが面倒くさがったことを代わりにすることなどが該当します。親が子どもの要求を過剰に聞き入れることは、過保護につながります。
「甘えさせる」は子どもの精神的な欲求を満たすこと
「甘えさせる」は子どもの精神的な欲求を満たすことであり、子どもに親の愛情を確認させる行為でもあります。
甘えさせることは、親という絶対的にあんしんできる場所があることを子どもに理解させます。
子どもにとっての絶対的にあんしんできる「基地」があることが、外に出てチャレンジすること、ひいては自立することにつながっていくため、重要だといえます。
また、甘え方は子どもによって異なり、頻繁に親とのコミュニケーションをとりたがるタイプや、「ママ、来て」と注目してほしがるタイプもいます。
「甘えさせる」ことはよいこと?

「甘え」というと悪いイメージを持ってしまう方もいるでしょう。しかし、十分に甘えさせることで、子どもの気持ちは満たされて、自立心が高まっていきます。
子どもが甘えるときは、自分の方へ親の意識を引きたいとき、自分を大事にしてくれるか確認したいとき、不安からスキンシップを求めるときなどです。その過程で、わがままをいってしまい、親を困らせることもあるでしょう。
子どもはこれらの行動が受け入れられると、「親から愛されている」とあんしん感を得られ、心が満たされます。何度も親に甘えさせてもらうことで、子どもは自分に自信がつき、段々自立心が高まっていきます。
子どもを甘やかすことによる悪影響

子どもを甘やかすことは、過保護や過干渉につながります。過保護や過干渉の状況で育った子どもは、物理的・金銭的なところで要求が叶っても、精神的には満たされていない状態です。
つまり、子どもは親に正しく甘えることができず、自立心の成長が妨げられてしまうことにつながるでしょう。
子どもを甘やかす行為は、「なにかあっても親が助けてくれる」「親に任せよう」という、他力本願な考えが根付くリスクがあります。子どもは自分の意思で行動せず、物事に対して、責任感を持てなくなる可能性があります。
また、相手の気持ちを考えることも苦手になってしまい、自己中心的な考え方になってしまいます。社会に出たとき、対人関係で問題が出てきて、生きづらさを感じてしまうでしょう。
適度に「甘えさせる」ことによるよい影響もある
適度に「甘えさせる」ことによって、親子の信頼関係の構築や、子どもの心に癒しを与えられるなど、プラスになることがあります。
また、自己肯定感も高くなるメリットもあるでしょう。親に甘えさせてもらうことによって、子どもは、「自分は大切にされている」「自分はここにいていいんだ」など、自分の存在を肯定できるようになります。
親子の信頼関係がしっかりしていることで、子どもは幸せを感じられ、あんしんできます。精神的に安定した子どもに育ち、家庭や学校でも元気に楽しく過ごせるでしょう。
子どもが親に甘えてくる理由

子どもが親に甘えてくる理由には、かまってほしい、寂しい、親の愛情を求めているなどの理由があります。
注意点として、子どもが親に甘えてくるとき、親の愛情を試していることもあります。子どもは自分が愛されているか、不安な気持ちを持っている可能性があるため、子どもが甘えてきたときは応えることが大切です。
しっかり甘えさせることにより、子どもの気持ちは満たされ、「親に愛されている」という自信がつくでしょう。
子どもは何歳まで甘えさせてよいのか?

子どもの心の自立には、甘えさせることが重要です。
個人差はありますが、子どもは心が自立していくと、自然に親から離れていきます。子どもの成長とともに次第に甘えてこなくなるため、年齢はそこまで気にしなくても、問題ないでしょう。
子どもが親から離れ、自立するときがくるまでは、甘えをしっかり受け止めるのがよいでしょう。
家族内で「あんしん」できる環境を構築しよう
子どもが甘えられるように家族内で、「あんしん」できる環境を構築しましょう。そのためには、子どもが素直でいられる環境を作ることが大切です。素直でいられる環境は、子どもが自分の気持ちをいいやすいかどうかが重要になるでしょう。
素直でいられる環境にするためには、子どもの話をしっかり聞き、円満な夫婦関係を築くことが必要になります。
夫婦仲が悪い状況は、子どもの成長にも悪影響をおよぼします。両親がいつも喧嘩をしていると、「自分も怒鳴られたり、危害が加えられたりするかもしれない」と子どもは怯えてしまい、あんしんできる家庭にはなりにくいでしょう。
子どもを不安にさせないためにも、子どもの前では、口論をしないようにするなど夫婦でルールを決めておくことをおすすめします。
「甘やかす」と「甘えさせる」を区別して子どもの自立を助けよう

親が子どもをしっかり甘えさせることで、子どもは満足して、自信をつけていくでしょう。仕事に追われていて、子どもを優先することが難しいときであっても、子どもが甘えてきたときはできるだけ応えましょう。
ただ、無理に甘えさせる必要はありません。あくまで子どものペースで、甘えにきたときのみでよいです。また、「甘えさせる」は「甘やかす」とは違うことにも注意が必要です。
ぜひ、本記事でとり上げた内容を参考に、「甘やかす」と「甘えさせる」の違いを意識して、子どもの自立心を引き出していきましょう。


