叱ると怒るはどう違う?効果的な叱り方やNG例について詳しく解説
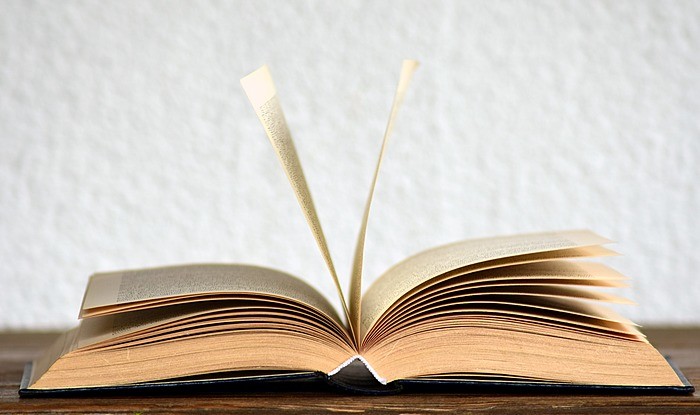
叱ると怒るとは何が違うのか、大人でもきちんと理解していないこともあるでしょう。本記事では、叱ると怒るの違い、怒ることは子どもにとってマイナスになるのか、効果的な叱り方などを紹介します。子どもが悪いことをしたとき、どういう対応がよいか悩む方は参考にしてください。
「具体的にどうしたら怒るから叱るになるの?」
「子どもに対してどういう叱り方はよくないのだろう?」
「叱る基準って必要なの?」
このように、叱ることに対して疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、叱ると怒るとでは意味が違うこと、子どもに対する叱り方のポイント、やめた方がよい叱り方についてなど紹介します。
この記事を読むことで、叱ると怒るの違いに気づき、子どもへの適切な叱り方なども見えてくるでしょう。また、子どもに注意しなければならないときに、どのようないい方をした方がよいかもわかってきます。
怒るのではなく正しいことを伝える方法を身に付けたい方、子どもとの向き合い方に悩んでいる方は、ぜひ、参考にしてください。
叱ると怒るの違いとは
叱ると怒るの違いは、行動理由が他人のためか、自分のためかという点があります。「叱る」の場合は、相手に対して助言をすること、アドバイスをすることであり、「怒る」は自分の感情をぶつけることです。
字の成り立ちを見ても、この2つの字の意味が異なることがわかります。叱るは「口」と「七」で構成されています。「七」は「しち」と読みますが、「しっ!」と強く声を発する意味を持ちます。
「叱」は、強い口調で相手に何かを伝えることを表現した漢字です。
怒るは「女」「又」「心」で構成されています。「又」は「手」を意味し、心に手を当てて怒っている女性を表した漢字です。自分の感情を表していることがわかるでしょう。
怒ることによるデメリット
親が怒ることで、子どもは委縮してしまい親子の間に距離感ができてしまう可能性があります。子どもは、怒っている側の言葉より感情を受取るため、怒って大きな声を出されれば恐怖心でいっぱいになってしまうでしょう。
何度か怒られることで「親は怒るから怖い」という意識が強くなり、心を開いてくれなくなる可能性があります。
怒ってばかりいると子どもとのコミュニケーションがとりにくくなるため、怒るではなく助言やアドバイスをする「叱る」という方向に変えていくようにしましょう。
効果的な6つの叱り方

叱るときの注意点として、叱り方によって伝えたい内容が正しく伝わるか、伝わりにくくなってしまうかは変わってくるでしょう。
子どもに伝わりやすい効果的な叱り方は、叱る理由を明確にして伝えることです。相手が子どもの場合は説明が長く、難しい言葉を使うと理解できないこともあります。
そのほかにもポイントはあります。具体的に紹介しているため、ぜひ、参考にしてください。
叱る場所や状況に気をつける
人がたくさんいる場所、騒がしい場所、友達の前などは、子どもの意識がそっちに向かってしまうため叱っても、その内容が頭に入りにくいことがあります。叱るときは帰宅してからなど、お互いが落ち着いて会話ができる環境になるよう、気をつけましょう。
特に、友達の前で叱ることはやめましょう。反省するよりも、友達に見られて恥ずかしい気持ちが先行する可能性が高いです。恥ずかしい思いをさせて、子どもの心を傷つけてしまうこともあるでしょう。
要点のみを伝える
叱った内容を子どもがきちんと理解できなければ、叱る意味が薄れてしまいます。叱る内容について、子どもがわかりやすいように要点のみを伝えるようにしてください。
たとえば「お店のなかでは走りません」「話を聞くときは静かにして相手の目を見て」など、短くシンプルに伝えるとよいでしょう。理由をわかってもらおうと長々話すと、何を叱られていたか子どもに伝わりにくくなります。
その場で叱ることが大事
叱るタイミングは子どもが悪いことをした「今」です。あと回しにすると子どもの記憶に残っていない場合もあるため、効果が薄れてしまうでしょう。過去のことを持ち出されても、身に覚えがなくなってしまっている場合は、子どもが納得しない可能性があります。
子どもの目線に合わせ大きすぎない声で叱る
子どもが恥ずかしい思いをしないように、子どもだけに届く声の大きさで、目を見て叱ることが大切です。叱られて恥ずかしいという気持ちで頭がいっぱいになると、話の内容が入ってこなくなる恐れがあります。
また、叱ったときの声の大きさや口調も怖いと、子どもが萎縮してしまうこともあるでしょう。つい大きな声で叱ってしまう方は、子どもが落ち着いて話を聞けるように、静かな声で伝えることが大切です。
行動に対してのみ叱る
子どもの人格を傷つけるようないい方や、ほかの子どもと比較するような発言は、子どもの自信喪失につながる恐れがあります。叱られた内容より、人格を傷つけられたことが心に残ってしまいかねません。
叱るときは、子どもが自分の行動がよくなかったと理解すればよいため、行動によって起きることのみに着目して指摘するようにしましょう。
叱る内容を増やさない
叱る内容を増やすと、何のことで叱られていたのか子どもがわからなくなる可能性があります。
たとえば、今日の夜にお風呂に入らなかったことを叱っていたのに、いつの間にか1週間前の忘れ物の話になっていたなどです。過去のこと、ほかのことは持ち出さず、今の出来事のみ叱ることが大切です。
人間性を否定する叱り方はNG
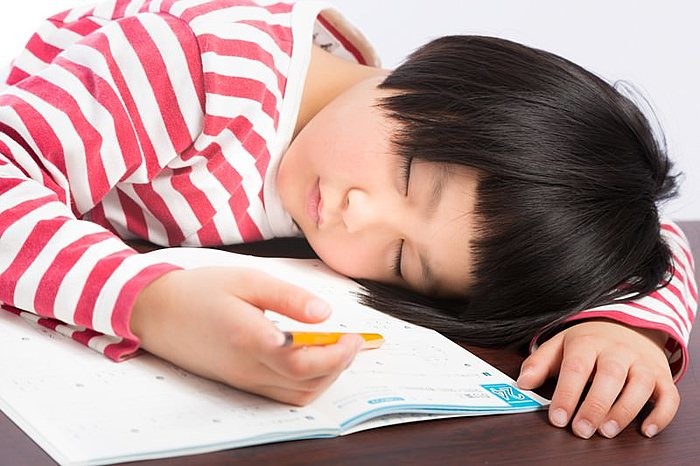
人間性を否定する叱り方は、子どもが自分に自信をなくす可能性があるため、やめた方がよいでしょう。
たとえば、「なんでそんな悪い子なの?」「こんなこともできないの?」「そんなこともわからないなんて情けない」というような言葉を使ったいい方です。
このような言葉をいわれることで、子どもは「自分はだめな子どもなんだ」と自信をなくすだけでしょう。
両親の間で「叱る基準」を決めておこう

叱ることが多すぎると本当に大切なことが伝わりにくくなり、子どもの心を傷つけてしまう場合もあります。そのため、両親の間で「叱る基準」を決めておきましょう。
「叱る基準」を決めて、両親で共通の認識が持てれば冷静になれる材料にもなります。片方が叱りすぎているときに、片方が「それはそこまで叱ること?」と疑問を投げて制止することもできるでしょう。
子どもに対しては「叱る」ができるようにしておこう

叱ると怒るの違いを理解して叱っているつもりでも、ついつい感情的に怒っているような状態になっていることもあります。
いいすぎてしまった、と気づいたときはそのことを子どもに謝りましょう。また、感情的になっているときは一呼吸おいて、冷静になることが大切です。気持ちには余裕を持って子どもと向き合ってみましょう。
子どもに対しては「叱る」ができるように、感情的な話ではなくそのとき問題となった要点のみを伝えるなど、気をつけましょう。

