生後3か月の赤ちゃんに与えるミルクの量は?赤ちゃんにとって適量か確認する方法も併せてご紹介

生後3か月の赤ちゃんは、どの程度のミルクを飲むかご存じでしょうか。この記事では赤ちゃんが飲むミルクの量や満足しているときのサイン、授乳時に気をつけておきたいことを紹介しています。赤ちゃんの授乳に心配ごとがある方はぜひ、こちらの記事を参考にしてみてください。
「生後3か月の赤ちゃんってどの位ミルクを飲むの?」
「赤ちゃんがミルクをきちんと飲めているのか全然わからない」
「赤ちゃんにミルクをあげるとき、注意点って何かある?」
など、赤ちゃんの授乳に関して疑問や不安がある方もいるのではないでしょうか。
本記事では、生後3か月の赤ちゃんが飲むミルクの量や、十分飲めているかどうか確認する方法を紹介します。この記事を読むことで、赤ちゃんに与えるミルクの量の目安がわかり、しっかりミルクを飲めているか確認できるでしょう。
またミルクを飲んでくれない理由や、ミルクをあげるときの注意点を紹介しているため、赤ちゃんに適切にミルクをあげられるようになります。
生後3か月の赤ちゃんが飲むミルクの量が気になる方、ミルクを飲んでくれなくて困っている方はぜひ、こちらの記事をチェックしてみてください。
記事のまとめ
- 生後3か月の赤ちゃんの1回のミルク量は約160〜200mlで、体重増加や機嫌で確認できる。
- ミルクを飲まない理由には温度や授乳体勢などが考えられ、適切な対処が必要である。
- ミルク作りには軟水を使用し、授乳後は赤ちゃんを縦抱きしてゲップを促すことが大切である。
生後3か月の子は1回あたり「160~200ml」のミルクを飲む
赤ちゃんが飲むミルクの量は、赤ちゃんの成長とともに少しずつ増えていきます。生まれた直後はごく少量しか飲めないのですが、月齢が進むごとに胃が大きくなり、1回に飲む量も1日に飲む量も増えていくでしょう。
生後3か月では、1回の授乳で約160~200mlのミルクを飲めるようになっています。
ここでは赤ちゃんの月齢ごとに、目安となるミルクの量や飲ませる間隔などを紹介します。
生後2〜3か月
生後2~3か月の赤ちゃんは、1回で約140ml、1日で約840mlのミルクを飲むでしょう。赤ちゃんにミルクを与える間隔は4時間ごとで、1日に6回、与えることになります。
赤ちゃんのミルクを飲む量は、個人差が大きいでしょう。この時期の赤ちゃんは、様子を見ながら、ミルクの量を調整することが大切です。
生後3〜4か月
生後3~4か月の赤ちゃんのミルクの量は、1回で約180~220ml、1日で約900~1100mlが目安になります。授乳の間隔は、4~5時間ごとです。
生後3~4か月になると、赤ちゃんの授乳リズムが整ってきて、毎日同じ時間帯に授乳するようになるでしょう。しかし飲んだり飲まなかったりと、赤ちゃんがミルクを飲む量にムラが出ることがあります。
また、この頃から赤ちゃんがなかなかミルクを飲まずに遊んでいることがあるでしょう。ミルクを飲まずに遊んでいても、赤ちゃんが満腹になっているわけではないこともあるため、すぐ授乳を止めないように気をつけてください。
ミルクの量が十分かどうかの確認方法

赤ちゃんにミルクを与えていても、あまり飲んでくれなかった場合、十分に飲めているかどうか心配になることもあるでしょう。ミルクを授乳している場合は飲んだ量がわかりやすいのですが、母乳を授乳している場合はどれだけの量を飲んだのかわかりづらいということもあります。
ここからは、赤ちゃんが十分にミルクを飲めているかどうか、確認する方法を紹介します。赤ちゃんが飲むミルクの量が足りている場合は、以下のようなサインが見られますので、確認してみてください。
体重が増えている
赤ちゃんの体重が、生後0~3か月頃までの間は1日に25~30g、生後3~6か月は1日に約15~20g、生後6~12か月で1日に約10~15g増えていれば、特に問題はないでしょう。
これは、厚生労働省の「乳幼児身体発育評価マニュアル」にある、赤ちゃんに期待される体重の増加量です。
赤ちゃんの成長タイプには、生後半年まで急激に成長するものの、その後はゆるやかになっていく一般型や、最初は一般型よりさらに急激な成長をしてその後横ばいになる立ち上がり型があります。ほかには、最初はゆるやかに成長し、途中で追いつく追いつき型もあります。
赤ちゃんの体重が増えなくても、成長には個人差があるため、ほかに問題がなければあまり心配する必要はないでしょう。
ぐずることが少ない
赤ちゃんが毎日機嫌のよい様子を見せていて、ぐずることが少ないようであれば、与えているミルクの量は十分でしょう。
ミルクが足りていない赤ちゃんはぐずったり、おっぱいを探す仕草をしたり、手を口に持って行くようにすることがあります。もしこれらのサインが見られたら、与えているミルクの量が足りない可能性があります。その場合は、ミルクを与えてあげましょう。
おしっことうんちがきちんとでている
薄い黄色のおしっこが普段どおりに出ていれば、ミルクの量は足りています。おしっこの色が濃くなったり、量が減ったり、おしっこの回数が少なくなった場合は、足りていない可能性があるでしょう。
赤ちゃんがどの程度うんちをするかは、個人差があります。特にミルクではなく母乳で育児している場合は、うんちがゆるくなり、回数が多くなりやすいことが特徴です。
ミルクや母乳の量が減ってくると、赤ちゃんのうんちが硬くなることがあります。水分の摂取量が減る離乳食の時期以外で、赤ちゃんのうんちが硬くなった場合、ミルクの量が足りていない可能性があるでしょう。
赤ちゃんがミルクを飲んでくれない理由として考えられること

赤ちゃんがミルクを飲まないときは、何か理由があって飲めなくなっている可能性があります。そのため、赤ちゃんがミルクを飲まなくても、授乳の必要がないとすぐに判断しないよう気をつけてください。
赤ちゃんがなぜミルクを飲んでくれないのか、考えられる理由を紹介します。赤ちゃんに与えているミルク自体が飲みにくくなっている場合や、赤ちゃん自身が飲みたがっていない場合があるため、参考にしてみてください。
ミルクの温度が高い
赤ちゃんに与えるミルクの温度が高すぎると、赤ちゃんがミルクの熱さを不快に感じてしまい、飲んでくれないことがあります。
ミルクを作るときは高い温度のお湯で作りますが、赤ちゃんに与えるまでに、人肌程度にきちんと冷ましましょう。
ミルクの温度を調べるために、腕の内側を上に向け、作ったミルクを少したらして人肌程度かどうか確認してみてください。もしミルクの温度が高かった場合は、冷水を溜めた容器に哺乳瓶を入れて冷ましましょう。
お腹がすいていない
授乳する時間になっても、赤ちゃんのお腹がすいていないと、ミルクを飲まないことがあります。
赤ちゃんは毎回、同じ量のミルクを飲むと決まっているわけではありません。前の授乳時にミルクをしっかり飲んでいた場合、なかなかお腹がすかず、ミルクを欲しがらないこともあるでしょう。
赤ちゃんが欲しがる量に合わせて、ミルクを飲ませてあげるようにしましょう。
赤ちゃんにとって飲みづらい
保護者が気づかないうちに、赤ちゃんにとって、ミルクを飲みづらい状態にさせていることがあるでしょう。考えられる理由は、赤ちゃんの授乳時の体勢や哺乳瓶の乳首の形、哺乳瓶の角度などです。
赤ちゃんを横抱きにしてミルクを与えると、満腹を感じやすくなり、あまり量を飲めなくなる可能性があります。また、哺乳瓶の角度に飲みづらさを感じている場合もあるため、哺乳瓶の乳首部分に空気が入らないように、かたむけてあげるようにしましょう。
哺乳瓶の乳首の形によって、ミルクが出やすかったり出にくかったりします。勢いよくミルクが出てくるようなタイプでは、赤ちゃんが嫌がってしまうこともあるでしょう。
ゲップが出なくてお腹が圧迫されている
赤ちゃんがミルクを飲んだ後にゲップをしていない場合、お腹にたまった空気が原因でミルクを飲めなくなっている可能性があります。
赤ちゃんはミルクを飲むときに、ミルクと一緒に空気を飲んでいます。通常は授乳後にゲップをさせることで空気を出せるのですが、ゲップが苦手な赤ちゃんもおり、ゲップが出ないこともあるでしょう。
ゲップが出ないことで赤ちゃんのお腹に空気がたまり、お腹がはって苦しい思いをするだけでなく、ミルクを飲んでも吐き戻しやすくなってしまいます。
ゲップを出しやすくするために、授乳した後は赤ちゃんを縦抱きしましょう。背中をパンパン叩く必要はありません。
出典:授乳後、ゲップを出さなくても大丈夫?|浜松市子育て情報サイト ぴっぴ
ミルクを与えるときの注意すべきこと

赤ちゃんにミルクを与えるときに、注意しておきたいポイントを紹介します。
赤ちゃんに与えるミルクは、ただ作ればよいというものではないでしょう。ミルクを作るための水や、温度には気をつける必要があります。また、ミルクの作り置きといったこともおすすめはできません。
赤ちゃんにミルクを与える際は、以下のポイントを把握しておきましょう。
ミルクを作るときは軟水を使う
ミルクを作るときに使う水は、軟水にしましょう。日本で暮らしている方の場合、水道水もミネラルウォーターも軟水が多いため、あまり心配はいりません。
硬水と軟水の違いは硬度にあり、日本では硬度100mg/L以上が硬水とされています。硬水には、カルシウムやマグネシウムが多く含まれているでしょう。
赤ちゃんに与えるミルクにはミネラルが含まれているため、硬水でミルクを作ってしまうと、ミネラルバランスが崩れてしまいます。軟水にはミネラル分があまり含まれていないため、赤ちゃんのミルクを作るための水として向いています。
水道水を使用する場合は沸騰させる
水道水を使ってミルクを作ることはできますが、その場合は10分以上、沸騰させるように気をつけましょう。
水道水は、塩素を使って殺菌されています。しかし塩素が水の中の有機物と化学反応を起こすと、発がん性が認められた「トリハロメタン」が発生します。トリハロメタンは、水道水を10分以上沸騰させることで除去可能です。
ただし、10分以上沸騰させた水からは、殺菌作用を持つ塩素も除去されています。水を作り置きする場合は冷蔵庫に入れ、2~3日以内で使い切りましょう。
水道水を沸騰させるのが面倒な場合は、浄水器を使うことで、水道水の有害物質を取り除けます。
出典:《おかやまさんぽメールマガジン》 第12号|岡山産業保健推進センター
ミルクをあげる量に気をつける
赤ちゃんにミルクを飲ませすぎないように、気をつける必要があります。
赤ちゃんが泣いているときに、お腹が減っているのではと安易に考えてミルクを与えてしまうと、ミルクのあげすぎになってしまう可能性があるでしょう。赤ちゃんが泣いていてもお腹がすいていることが原因とは限らないため、すぐにミルクをあげるのは避けてください。
粉ミルクを作るときは、正確な量で作ることも大切です。自己判断で量を減らしたり、増やしたりしないようにしましょう。
作ってから2時間たったものは処分する
赤ちゃんが飲んでくれず、作ってから2時間以上経過したミルクは処分し、赤ちゃんには与えないようにしましょう。
これは、作られたミルクは有害な細菌が増殖しやすい環境であるためです。2時間放置したミルクを赤ちゃんに与えるのは、リスクが高くなります。
赤ちゃんにミルクを与えるときは、作りたてをあげるようにしてください。
出典:乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン |厚生労働省
心配なときは病院やクリニックに相談しよう
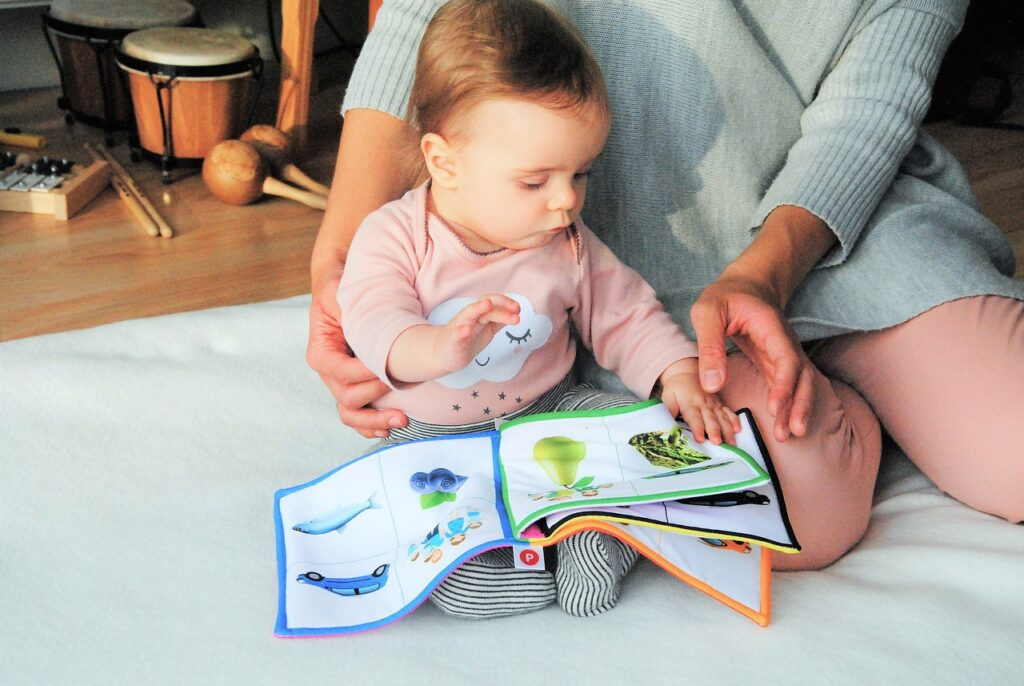
赤ちゃんは月齢によって、1回に飲むミルクの量や1日に飲むミルクの量は少しずつ増えていきます。しかし赤ちゃんのミルクを飲む量には個人差があるため、なかなかミルクを飲んでくれない赤ちゃんもいるでしょう。
赤ちゃんがミルクをあまり飲まなくても、普段と様子が変わらず機嫌よくしていれば、それほど心配はありません。この記事を参考に、適切に作ったミルクを赤ちゃんにあげてみてください。
もし赤ちゃんが飲むミルクの量に不安がある場合は、病院やクリニックに相談してみましょう。病院やクリニックに相談することで、赤ちゃんの発育に問題はないか診てもらえるので、あんしんできるでしょう。


