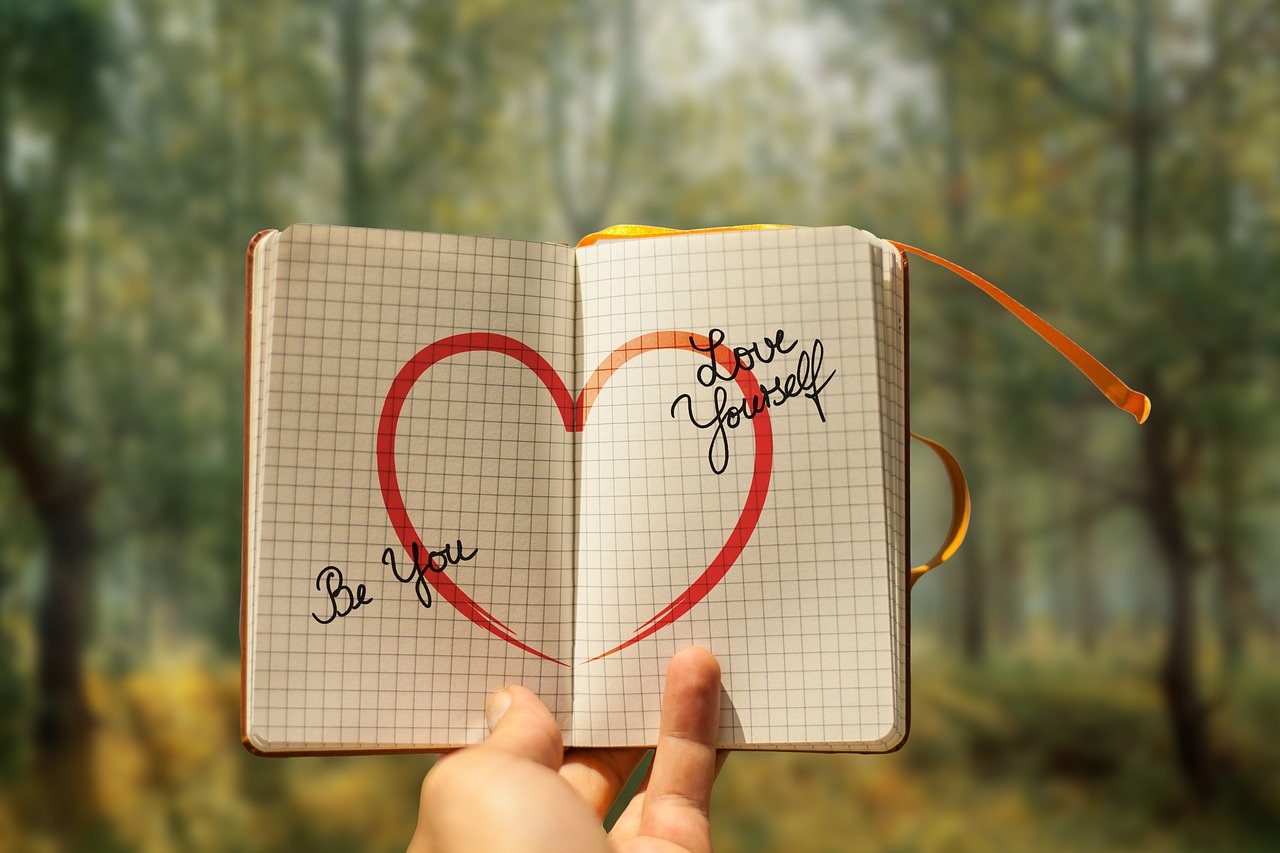出生時育児休業とはどんな制度?対象期間や社会保険料免除・給付金の制度についても解説

出生時育児休業を利用する際、申請の手続きで気をつけることや育児休業との違いをご存じでしょうか。この記事では、出生時育児休業について基本情報から申請方法など詳しく解説します。制度を使用し、仕事と家庭の両立をしたい方は、ぜひ、こちらをご確認ください。
「出生時育児休業はいつからあった制度なんだろう」
「育児休業給付を受ける条件ってどんな内容かな?」
「出生時育児休業の申請って、誰にするの?」
このように出生時育児休業に関して、疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
本記事では、出生時育児休業という制度の特徴、育児休業との違い、出生時育児休業中に仕事をする場合の手続きについてなどを紹介します。
この記事を読むことで、出生時育児休業の制度について理解が深まります。正しい知識を持ってこの制度を活用できれば、女性だけでなく男性も仕事と家庭のバランスを取りながら、育児に参加しやすくなるでしょう。
これから子が生まれるという方、出生時育児休業について詳しく知っておきたい方は、本記事をご一読ください。
記事のまとめ
- 出生時育児休業は2022年10月から施行され、男性が育児に参加できる制度である。
- 最大4週間の休業を2回に分けて取得可能で、申請手続きが必要である。
- 育児休業との違いや、社会保険料免除、給付金の受給条件についても解説している。
出生時育児休業(産後パパ育休)は2022年10月1日から施行された
男性が育児にかかわる制度として、出生時育児休業(産後パパ育休)があります。育児休業は知っていても、出生時育児休業については知らない方も多いのではないでしょうか。
出生時育児休業とは、男性が出産直後の配偶者をサポートするために利用できる制度で、2022年10月1日から施行されました。以下では、この制度の具体的な内容について紹介します。
出典:産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます|厚生労働省
出典:Q20「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?|厚生労働省
基本的にすべての男性労働者が対象となる
出生時育児休業は、男性労働者の育児休業取得を促進するために設けられた制度で、男性版育休と呼ばれることもあります。
基本的にすべての男性労働者が対象となり、出生後8週間以内の子を養い、育てる場合に取得可能です。養子の場合も、生後8週間以内であれば取得の対象となり、この場合は女性労働者も対象です。
ただし、契約期間の満了日が設定されている有期契約労働者の場合、対象外となるケースもあるので注意が必要です。
子の出生の日から8週間経過後、6か月以内に契約が終了することが決定している場合は、取得の対象外となります。これは、育休の1歳6か月までに契約が終了する予定が決まっていない要件に準じたものです。
また、雇用期間が1年未満の労働者や、週の所定労働日数が2日以下の労働者も、労使協定により取得対象から外れます。該当しないか、事前に確認しておきましょう。
出典:Q20「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?|厚生労働省
出典:有期雇用労働者の育児休業や介護休業について(p.1)|厚生労働省
出典:育児・介護休業法のあらまし(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)(p.13)|厚生労働省
出生時育児休業は最大4週間取得可能
出生時育児休業は、子の誕生から8週間の期間内に、最大4週間の休業を2回に分割して取得できることが特徴です。たとえば、子の誕生後に2週間休み、その4週間後にさらに2週間休めます。
また、会社によっては独自の育児休暇制度が設けられている場合もあります。会社独自の育児休暇制度がある場合は、出生時育児休業の4週間に加え、その制度に基づく休暇を追加で取得できるため、合計でさらに長い期間休める可能性があるでしょう。
出典:産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)(p.7)|厚生労働省
出典:男性育児休業 取得マニュアル(p.41)|埼玉県
「育休制度」との違いは?

「育休制度」とは、育児休業制度のことであり一般的に「育休」と呼ばれてきたものです。しかし、出生時育児休業と混合される方もいるのではないでしょうか。
育休と出生時育児休業はどちらも育児を目的としていますが、それぞれ異なる特徴を持っています。ここでは違いを紹介します。
まず、対象となる期間ですが、育休は子が1歳になるまで取得可能です。条件によっては最大2歳まで延長できます。出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度です。
申し出期限も違いがあります。育休は休業開始予定日の1か月前までに申し出る必要がありますが、出生時育児休業は2週間前までです。期限については注意してください。
また、制度の内容の違いとしては、育休の取得は男女問われませんが、出生時育児休業の対象者は主に男性です。
就業の可否にも大きな違いがあり、育休では休業中の就業が原則として認められていません。しかし、出生時育児休業は労使協定がある場合に限り、労働者が同意した範囲で勤務することができます。
従って、育休は長期的に育児に専念する制度であり、出生時育児休業はより短期的かつ柔軟にサポートができる制度となっています。
出典:Q20「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?|厚生労働省
出典:産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)(p.1)|厚生労働省
出生時育児休業期間中の就業に対して必要な手続きとは?

出生時育児休業期間中に就業を希望する場合、手続きが必要です。休業開始予定日の2週間前までに、会社に就業できる日程や時間帯、テレワークの希望などを申し出る必要があります。
手続きは、雇用主や人事部など、指定された部署に提出します。提出先も事前に確認しておくことが重要です。
また、出生時育児休業の開始後、新たに就業を希望する場合は、その時点で会社に申請し、会社の同意を得たうえで就業条件を確認、手続きを進めてもらいます。その際も開始予定日の2週間前までに申し出ることが必要になります。
出生時育児休業期間中に複数回にわけて就業する場合は、それぞれのタイミングで事前に申し出が必要です。
出典:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改定内容の解説(p.14)|厚生労働省
出典:Q20「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?|厚生労働省
育児休業給付を受けられる場合もある
受給資格を満たしている方は、育児休業給付を受けることが可能です。原則として、育児休業開始から最初の180日間は、休業開始前の賃金(日額)の67%が支給されます。育児休業開始から181日目以降は、賃金の50%が支給されます。
受給資格は、育児休業開始日前2年間に、一定の勤務実績(被保険者期間が通算して12か月以上)があることです。
また、この手続きをするにあたっても申し出が必要になります。育児休業給付は、会社側に代行してもらう形が一般的です。代行してもらう際は、申請者自身が必要書類(住民票や母子健康手帳の写しなど)を準備し、会社に提出しましょう。
出典:Q20「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?|厚生労働省
出典:出生時育児休業(産後パパ育休)とは?|小林裕彦法律事務所
出典:育児休業給付の内容と支給申請手続(p.5)(p.18)|厚生労働省
社会保険料の免除のためには申し出が必要
要件を満たせば、申請の手続きを通じて育児休業期間中の社会保険料が免除されます。対象となるのは、本人負担分と会社負担分の両方です。
社会保険料の免除の手続きは、まず会社へ育児休業申出書を提出します。この申し出をもとに、会社側が免除における必要書類を年金事務所に提出し、受理されると保険料の免除が開始されます。
社会保険料の免除を受けるためには、月末が育休期間中であること、もしくは同一月内で14日以上の育児休業を取得していることが条件です。
賞与にかかる保険料は、1か月以上連続して育児休業を取得した場合にのみ免除されます。育児休業を終了する時期などに注意し、手続きが適切に行われるよう確認してください。
出典:Q20「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?|厚生労働省
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構
出生時育児休業の制度や必要な手続きへの理解を深めよう

2022年10月1日から新たに施行された出生時育児休業は、父親が出産後に育児にかかわるための柔軟な制度です。本記事を参考に、出生時育児休業を利用するメリットについて考えるきっかけにしてみてください。
紹介したとおり、育休と出生時休業では申し出期限や就業の可否などに違いがあるので、混同しないよう注意が必要です。男性は両制度を併用することができるので、上手に活用するためにも、制度の内容を事前にしっかり確認しておきましょう。
また、出生時育児休業を使うためには、事前の申し出が必要です。希望する日程で利用できるように手続きの流れや申請方法、休業中の勤務に関する申請などについては、あらかじめ理解しておきましょう。
出典:令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について|厚生労働省