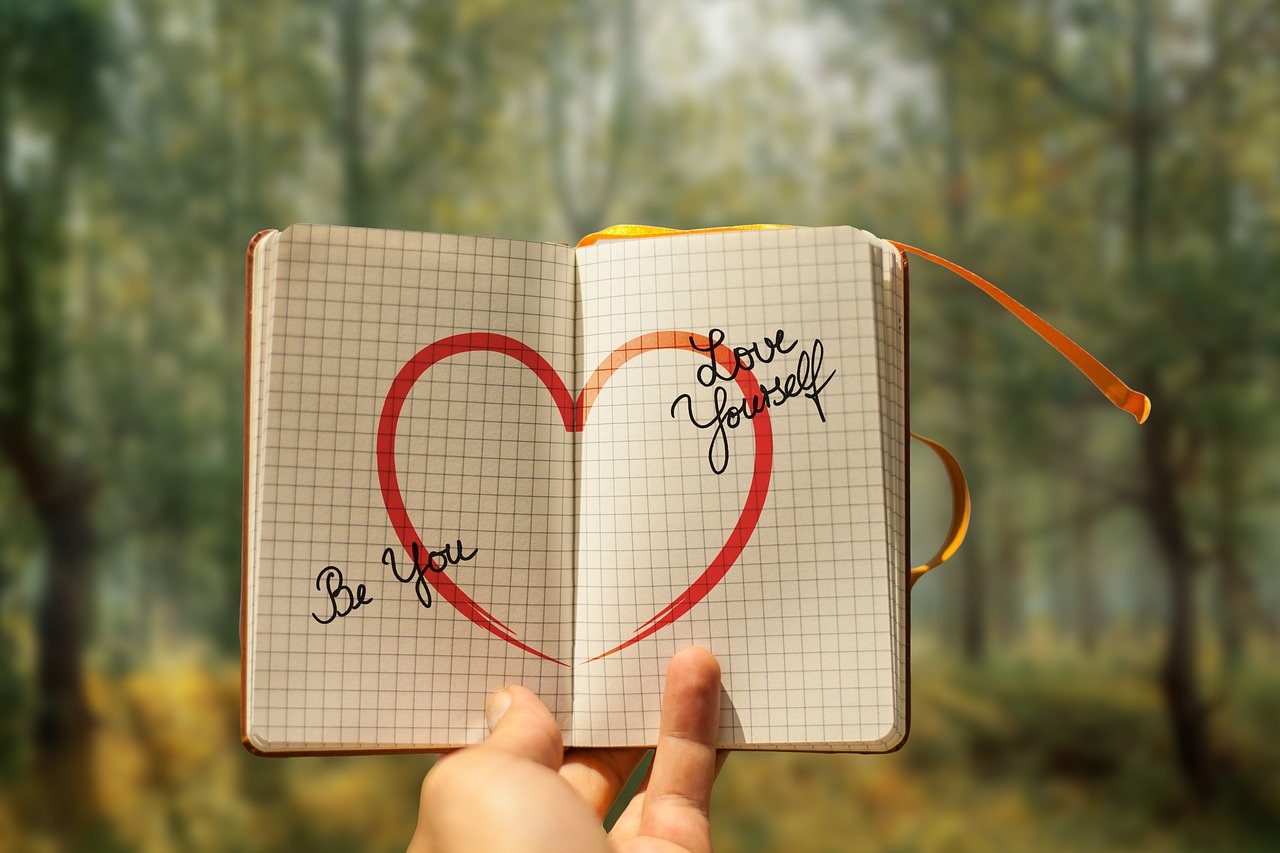みんなで楽しめる!バリエーション豊かな21種類のおにごっこをご紹介

「おにごっこ」と聞いて、どのような遊びを思い浮かべるでしょうか。本記事ではおにごっこをする方法や、さまざまな種類があることを紹介しています。子どもと一緒に、あるいは子ども同士で楽しく遊ばせたいと考えている方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
「おにごっこってただ追いかけっこをするだけではないの?」
「おにごっこってそんなに種類があるの?」
子どもの頃に、おにごっこをして楽しんだ方もいるでしょう。しかしおにごっこには多くの種類があることや、おにごっことは知らずに遊んでいる場合もあるのではないでしょうか。
本記事では、おにごっこの基本的な遊び方をはじめ、おにごっこの種類を詳しく紹介しています。この記事を読むことで、おにごっこには、20種類以上の豊富なバリエーションがあることがわかり、それぞれのルールを把握して遊べるようになります。
通常とは別のおにごっこを試してみたい方や、新しい遊び方を子どもたちに提案したい方は、ぜひ、こちらの記事をチェックしてみてください。
記事のまとめ
- おにごっこには多くの種類があり、基本的な遊び方を知ることで楽しみが増える。
- 21種類の遊び方を紹介し、それぞれのルールを理解することで新しい体験ができる。
- 子どもたちと共に、遊びの工夫をしながら楽しむことが重要である。
おにごっことは「おに(追いかける人)から逃げる」遊び
昔からある遊びのおにごっこですが、遊び方はとてもシンプルで、おに役と逃げる役にわかれ、逃げる子どもをおにが追い回します。
こういった基本的なおにごっこのほかに「ひっこしおに」「どろけい」などの、さまざまなバリエーションも存在します。また、遊び方にアレンジを加えることで、新鮮な気分で遊ぶことも可能でしょう。
おにごっこでも21種類!?

ここでは、おにごっこの21種類の遊び方を紹介します。
おにごっこで、友達と競い合い遊ぶ楽しさを知ることができるでしょう。また、体全体を使うことで、体をどう動かせばよいか学べます。
さまざまな種類のおにごっこは、それぞれ違う遊び方で楽しめます。そして、自分たちでより楽しめるように、工夫することも可能です。
新しいおにごっこの遊び方を知り、日々の遊びに取り入れてみてください。
おにごっこ
おにごっこは、追いかけるおに役と逃げる役にわかれ、追いかけっこをする遊びです。
おにごっこするときは、まずおにの役を決めます。その後におには10秒ほどカウントし、カウント中に、おに以外の子どもたちは捕まらないよう逃げましょう。10秒カウントした後、おには子どもたちを追いかけ、追いついてタッチすると、おにと役が入れ替わります。
おにの交代がスムーズでない場合は、交代するまでの時間を決めて行ってみましょう。
高おに
「高おに」は、おにに捕まらないように、子どもたちが地面よりも高い場所に逃げる遊びです。
高おにでは、おにが追いかけてきたときに、高いところに逃げることに成功した子どもは、おにに見つかってもタッチされません。段差や遊具など、高低差があるスペースで遊ぶのに向いています。
子どもたちが、ずっと高い場所に居続けるのを防ぐためにも「同じ場所には10秒間しかいられない」と決めておけば、おにがタッチするチャンスが生まれます。
また、おにが待ち伏せすることを防ぐために、子どもが高い場所から降りても数秒間はタッチできない、といったルールを付け加えてもよいでしょう。
高低差を利用した遊びなので、危険な場所には登ってはいけないと周知し、安全に配慮して遊んでください。
低おに
「低おに」は高おにとは反対に、子どもたちが木の下や遊具の下などに入って、おにから逃げ回ります。子どもが何かの下にいる間は、おにから身を守ることができます。
おにごっこを開始し、おにが10秒カウントしている間に、ほかの子どもたちは下に入れる場所を探しましょう。逃げ切れなかった子どもを捕まえたら、おには交代できます。
子どもたちが同じ場所に居続けられないように、1つの場所に避難していられる時間を制限するとよいでしょう。
氷おに
「氷おに」は、友達と協力しあって遊べるおにごっこの1つです。
氷おにでは、おににタッチされそうになった子どもは「こおり」ということで凍結できます。凍結している間はおにはタッチできませんが、凍結した子どももその場から動くことはできません。
ほかの子どもが「おゆ」といいながら凍結している子どもにさわれば、凍結していた子どもは再び動けるようになります。おにが子どもを捕まえたり、全員凍結させたりするまで続くというルールになっています。
おにが子どもをなかなか捕まえられない場合は、時間制限を設けて交代してみましょう。
いろおに
「いろおに」は、おにが指定したいろを探してさわることができれば、おにが近くにいても捕まることのない遊びです。
ゲームがはじまったら、子どもたちは「いろいろなんのいろ?」とおにに聞きましょう。おには好きな色を指定します。それから数秒ほどカウントした後、おには動き出し、指定した色にふれていない子どもを探しましょう。子どもがおにに捕まれば、おにと交代します。
1つの場所には1人しかさわれないといったように、ルールを追加することもおすすめです。
バナナおに
「バナナおに」では、おににタッチされた子どもはバナナの真似をします。
おにに捕まると、子どもは両手を上げ、バナナのように体を曲げたポーズで、その場に止まるのがルールです。ほかの子どもたちが、バナナとなった子どもの近くに寄り、皮をむく動作をすれば復活できます。制限時間が終了するか、全員をバナナにできれば終了です。
順番で、おに役を交代するとよいでしょう。
スイカおに
「スイカおに」は、おにに捕まったらスイカになるというおにごっこです。
おににタッチされてスイカになった子どもは、ほかの子どもが「パッカーン」といいながらスイカ割りのようなジェスチャーをしてあげることで、動けるようになります。おに役は、全員をスイカにするまで追いかけます。
おにの交代をスムーズにするため、時間ごとにおにを交代してみましょう。
カニおに
「カニおに」は、みんながカニのように動く遊びです。
遊ぶ前に、まず地面に少し離れた2本の線を描きます。2人のおにが決まったら、1人ずつ2つの線の上に立ち、待ち構えます。おに以外の子どもたちは、片方の線の手前に集まり、合図と同時に2本の線の向こう側まで逃げましょう。
おにに捕まった子どもは、ワカメとして線の上に立ち、ほかの子どもたちがとおり抜けるのを邪魔します。最後まで残った人の勝利です。
一緒に遊ぶ子どもの人数に合わせて、線を長くしたり短くしたり、調整してみてください。
たすけおに
全員でたすけ合いながら、おにから逃げる遊びが「たすけおに」です。
たすけおにでは、おにに捕まった子どもは動けなくなり、ゲームに参加できなくなります。しかし、ほかの子どもがタッチしたり、タッチに代わるアクションをとることで再び動くことが可能です。
おにが全員を動けなくするか、子どもたちが飽きてくれば終了にしましょう。
じぞうおに
おにに捕まると、子どもがおじぞうさんのポーズで仲間のたすけを待つ遊びです。
おじぞうさんになった子どもは、動けません。ほかの逃げている子どもが「お供え物をあげる」「拝む」ジェスチャーをすることで、おじぞうさんになった子どもを復活させられます。全員がおじぞうさんになってしまうか、子どもが飽きた場合は遊びを終了してください。
おじぞうさんになった子どもが足を広げて立ち、その足の間をくぐれば復活できるというアレンジも可能です。
ふえおに
「ふえおに」は、遊んでいるうちにおにの数がふえていく遊びです。
おには子どもを発見次第捕まえ、おにの仲間に加えてどんどんおにの数をふやしてきます。時間がたつと、逃げ続けるのは難しくなっていくでしょう。
最初に、制限時間を決めておきましょう。時間内におにが全員を捕まえられれば、おにの勝利で終了です。逃げ切った子どもがいれば、おにの敗北となります。何人で遊ぶかによって、おにの数を変えましょう。
手つなぎおに
「手つなぎおに」は、おにが手をつないで子どもたちを追い回す遊びです。
おにが子どもに追いついて捕まえたら、その子どももおにとして一緒に手をつなぎ、ほかの子どもを追いかけます。最後まで逃げ切れた子どもがいたら、その子どもの勝利になります。
手つなぎおにでは、おにの人数が4人以上になったら、半数ずつにわかれるルールでも問題ないでしょう。
でんしレンジおに
「でんしレンジおに」は、仲間との協力がカギとなるおにごっこです。
でんしレンジおには、通常のおにごっこと同じようにおにを決め、10秒カウントしてから逃げる子どもを追いかけてください。子どもは、おにに捕まった時点で動くのを止めましょう。
固まった子の周りを、仲間の子ども2人が手をつないで囲みます。しゃがんで「電子レンジで」といった後に、立ち上がって「チーン」といいましょう。固まっていた子どもは、再び動けるようになります。
仲間をたすけようと2人でたすけに向かっても、2人ともおにに捕まるハプニングが起こる可能性もあり、面白いでしょう。
がっこうおに
「がっこうおに」は、仲間をたすけるために少し長い言葉をいう必要がある遊びです。
おにを決め、おにが10秒カウントして待っている間に子どもたちは逃げます。おにはカウント後、子どもを追いかけましょう。おににタッチされた子どもは、その場に止まってたすけを求めます。
逃げている子どもが「キーンコーン、カーンコーン」といいながらタッチすれば、動けなかった子どもは再び動けるようになります。おにが子ども全員をタッチすれば、おにの勝利です。
あらかじめ遊ぶ時間を決めて行い、おにを交代していきましょう。
ひっこしおに
「ひっこしおに」は、自由にどこでも逃げることはできないおにごっこです。
遊ぶ際は、事前に地面に〇や□などの形の陣地を大きく描いてください。ゲームがはじまったら、ほかの子どもたちは陣地のどれかを選んでなかに入ります。おにが「ひっこし」といったタイミングで、子どもたちは今いる陣地とは別の陣地に入らなければなりません。
陣地から出てきた子どもは、ほかの陣地に入るまで、おにに追いかけ回されるでしょう。
ゾンビおに
「ゾンビおに」は、おに役がゾンビになり、子どもを追いかけ回す遊びです。
ゾンビ役を決めてゲームが開始したら、ゾンビ役の子どもはゾンビになって、逃げる子どもたちを追いかけます。子どもをタッチすれば、その子もゾンビに加わります。
おにではなくゾンビになりきるので、おによりも遅いスピードで追いかけることになるでしょう。そのため、通常のおにごっこよりも狭いスペースで遊ぶのがおすすめです。
かげふみ
「かげふみ」は、かげ(影)が出ていなければ行えない遊びです。
かげふみでは、おには逃げる子どもを追って捕まえるのではなく、かげをふめたらおにを交代します。
自分のかげをふまれないように、大きなかげにかくれるといった工夫ができます。未就学児であれば、かげの動きを楽しんでくれるでしょう。逃げる子どもが1人になるまで続けたり、かげをふまれた子どもがおにに加わったりする遊び方もできます。
ドロケイ
「ドロケイ(ケイドロ)」では、子どもたちが「泥棒」と「警察」にわかれて追いかけっこをします。
まず子どものなかから、少数の警察役を決め、牢屋の場所も決めましょう。警察が10秒カウントしている間に泥棒役の子どもたちは逃げますが、追いかけてきた警察に捕まると牢屋に入れられます。逃げている泥棒が捕まった泥棒にタッチすれば、解放できます。
制限時間を決めておき、制限時間内に泥棒が逃げ切れば泥棒の勝利となり、泥棒を全員捕まえることができれば、警察の勝利です。
ボールおに
「ボールおに」は、タッチではなくボールをあてて、おにを交代するおにごっこです。
おにはボールを持った状態で逃げる子どもを追いかけ、子どもにボールがあたるように投げます。ボールにあたらず、キャッチした場合はおにへの交代はありません。キャッチしたボールを遠くに投げて、おにを妨害できます。
一緒に遊ぶ子どもの人数によって、おにの人数やいくつボールを使用するか工夫しましょう。
かくれおに
「かくれおに」は、かくれんぼも一緒に楽しめるおにごっこです。
まずおにが決まったら、おには30~60秒の決められた秒数をカウントしましょう。その間にほかの子どもたちは逃げて、どこかにかくれます。おにが「もういいかい」と聞いてかくれている子どもたちから「もういいよ」という返事があったら、探しはじめましょう。
おにはかくれている子どもを探し、発見して捕まえたら交代できます。おにの交代が発生次第、最初から繰り返して遊んでみてください。
おおかみさんいまなんじ?
子どもの数が多いときは「おおかみさんいまなんじ?」がおすすめです。
まずおおかみ役を決めますが、保護者が行っても構いません。子どもたちは子ぶた役になり、家になる場所を陣地として決めましょう。おおかみは家から離れた場所で寝たふりをし、子ぶたたちが近づいてきて「おおかみさんいまなんじ?」と聞きます。
おおかみは、12時以外を答える場合は「いま9時」のように答え、寝たふりを続けましょう。「いま12時だぞ」とおおかみが答えた場合、おおかみはすぐに子ぶたを追いかけ、子ぶたたちは家に逃げ戻ります。
子ぶたを1人でも捕まえればおおかみの勝利で、全員逃げ切れば子ぶたの勝利です。
時間をあまり意識していない小さな子どもと遊ぶ場合は「おやつの時間、3時だぞ」といったように、日常のいつの時間かを伝えるようにしましょう。
さまざまなおにごっこをみんなで楽しもう!

おにごっこは、簡単なルールで遊べるものから、少し複雑なルールのものまであります。また、遊び方をアレンジすることで、より楽しく遊べるでしょう。
子どもの人数に合わせておにの人数を工夫したり、逃げる役の子どもがおにに加わったりして、遊び方の幅を広げることも可能です。
さまざまな遊び方を子どもに教えて、状況に合わせつつ、おにごっこを楽しんでみましょう。