子どもの「考える力」を伸ばす保護者の関わり方とは?「考える力」が求められる理由も解説
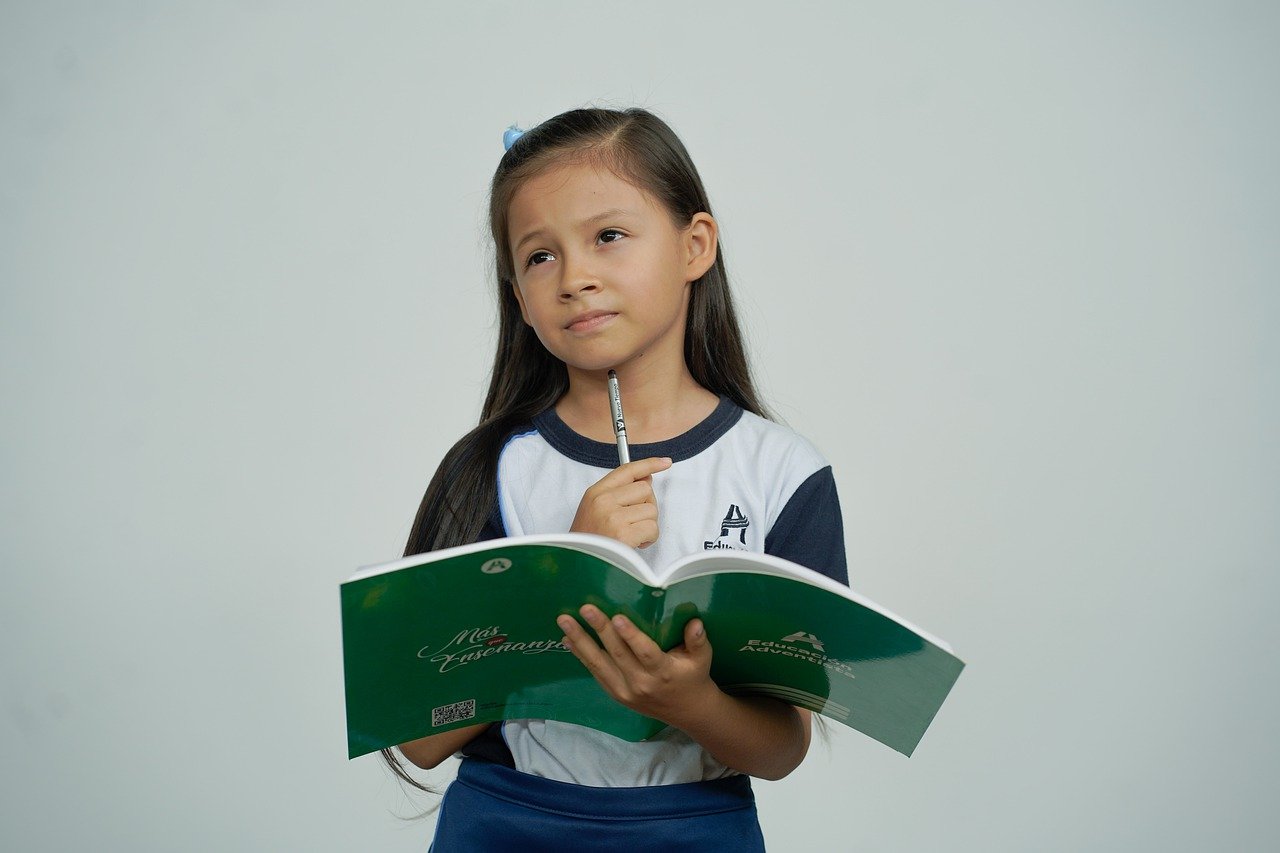
子どもの「考える力」の伸ばし方を知りたいという方はいませんか。本記事では、就学前に「考える力」を伸ばすことのメリットや、子どものために保護者ができるサポートについて解説します。子どもの未来を広げたいと考えている方は、ぜひ、本記事を参考にしてください。
「最近、「考える力」という言葉をよく聞くけど、どういうことだろう?」
「子どもの「考える力」を伸ばすためには、どうしたらいいの?」
など、子どもの思考力を伸ばすことに関心を持っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、幼児期の子どもの「考える力」が重要視されている背景について詳しく解説します。
また、「考える力」を伸ばすことのメリットや、将来的な影響についても解説しているため、この力を伸ばすことの重要性が理解できるでしょう。
さらには、保護者が実践できる具体的なサポートについても紹介しているため、自分の子どもに対して、適切な距離を保った関わり方ができるようになります。
子どもの可能性を広げてあげたいと考えている方は、ぜひ、この記事をぜひチェックしてみてください。
記事のまとめ
- 「考える力」は子どもの学習意欲や人間関係を形成する重要な要素である。
- 保護者のサポートを通じて、子どもは自分で考える力を身につけられるようになる。
- 試行錯誤を促し、適切な関わりを持つことで子どもを成長させていくことができる。
なぜ近年「考える力」が求められるのか
現在の学校教育では、「考える力」を重視する傾向が強まっています。
この傾向は幼児教育にも表れており、2022年度に改訂された学習指導要領のなかでは、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、「思考力の芽生え」が記載されています。
この背景には、目まぐるしく変わる社会状況が影響しているといえるでしょう。
急速に変化する世界では、単なる知識の暗記だけでは対応できないこともあります。情報を分析し、独自の視点で判断するためにも、考える力を養うことが大切になるでしょう。
子どもの「考える力」を伸ばすメリット

幼児期に培われた考える力は、小学校以降の学習意欲に大きな影響を与えると考えられています。
そのほか、円滑な人間関係を築くうえでも重要になるなど、生涯にわたって必要とされる力であるため、子どものうちに身に付けておくことが望ましいでしょう。
ここでは、考える力を伸ばすことで得られる具体的なメリットについて、詳しく解説します。
小学校以降の学習意欲が向上する
小学校では、頭のなかで考えて、答えを導き出す学習が主流になります。
そのため、幼児期に考える力を養っていない子どもの場合、「わからないからいいや」と学習意欲が低下してしまいやすくなるでしょう。
逆に、幼児期に考える力を養っていた子どもであれば、「どうすればできるようになるんだろう」と考えることが可能です。
新学習指導要領でも、「学びに向かう力」を幼児期から育むことで、小学校以降の学習意欲につながると考えられています。
特に、幼児期に経験した遊びや生活のなかでの気づきから探究へという学習につながるプロセスが、就学後のパフォーマンスの向上につながるといえるでしょう。
出典:資質・能力の三つの柱に沿った、幼児教育において育成すべき資質・能力の整理イメージ(たたき台)|文部科学省
「考える力」は生きていくために必要な土台を作る
文部科学省の学習指導要領では、「思考力、判断力、表現力」を、育成すべき資質・能力の三つの柱の1本と位置付けています。
このことから、子どもたちが成長し生きていくためには、「考える力」が不可欠と考えられていることがわかるでしょう。
「考える力」は、日々変化する環境のなかで、子どもたちが将来力強く生きていくための基礎となります。
また、幼児期から自分で考える習慣を身に付けることで、将来的に、問題から逃げずに向き合える大人へと成長できるでしょう。
人間関係を円滑にする
考える力は、円滑な人間関係を築くうえでも重要な役割を果たします。
たとえば、「なぜこの人は泣いているのだろう」「相手が幸せな気持ちになるにはどうすればいいだろう」と考えることで、子どもには共感や思いやりの心が育ちます。これはコミュニケーション能力の重要な側面です。
また、考える力を身に付けることで、相手に配慮できるようになるため、将来の良好な人間関係の基盤を作ることにつながります。
子どもの「考える力」を伸ばすために保護者ができること

子どもの考える力を育むには、日々の生活のなかで、保護者が意識的に関わることが重要です。
しかし、単に知識を与えるだけでは十分とはいえません。保護者のサポートとしては、子どもの思考を促し、成長を支援するような方法がふさわしいでしょう。
ここからは、日常生活のなかで実践できる、具体的なアプローチを紹介します。以下に挙げる方法を参考にしながら、子どもの考える力を育んであげましょう。
子どもが一人で考える時間を作る
子どもの思考は、大人に比べてゆっくりとしたプロセスをたどるため、急かしてしまいたくなることもあるでしょう。
しかし、大人が答えを急がせると、子どもが自ら考えることを中断したり、諦めたりする可能性があります。
子どもの考える力を伸ばすためには、一人で考える時間を十分に確保することが大切です。
たとえば、保護者が質問してから子どもが答えるまで、数秒待つようなルールを設けるのもよいでしょう。その間に、子どもは自分なりに考え、行動を起こしたり答えを出したりできます。
考える力を育てるために、子どもが疑問を持ったときには、少しヒントを出す程度にとどめ、自分で答えにたどり着く過程を大切にしてあげましょう。
間違っていてもやめさせない
子どもの考える力を伸ばすためには、試行錯誤を重ねることが大切になります。
子どもが間違っている場合、指摘したくなることもあるでしょうが、失敗することは成功と同じくらい価値のある学びです。
さまざまな方法を何度も試すことで、子どもは物事の因果関係に気づくでしょう。
子どもが悩んでいるときに保護者ができるのは、黙って見守ることです。失敗も貴重なプロセスであることを理解し、子どものチャレンジ精神を育んであげましょう。
子どもの疑問にすぐ答えない
考える力を養うためには、質問に対する答えをすぐ出すのではなく、自分で考える時間を持たせることが大切です。
子どもが疑問を持ったときは、考える力を育むチャンスと考えましょう。
子どもから質問を受けたときは、答えを返す前に「自分はどう思うか」を問いかけ、「なぜそう思うのか」、考えを引き出してください。
何度も質問されるのが大変なときもあるでしょうが、何気ない日々の会話こそが、考える力を育むことにつながります。
保護者が自分でやり方を考える手本を見せる
子どもには、教えるよりも手本を示し、自分で考えるように導くことが大切です。
たとえば、はじめての道具を使う際には、手取り足取り教えるのではなく、大人のまねをさせながら、子どもが自分なりに考えて、試行錯誤する機会をつくってあげましょう。
大人のしぐさや行動を観察し、自分で試すことで、子どもはさまざまなことを身に付けていきます。
最後に子どもと一緒に答えを見つける
子どもが自分で考える力をつけるためには、大人が答えを与えるのではなく、気づきを促すことが重要です。
まずは、子どもとの会話を広げて一緒に話し合いましょう。問いかけやヒントを通じて、新しい視点に気づかせることで、子どもの主体的な学びをサポートできます。
また、何かうまくいったときには、「やったね」「すごいよ」と一緒に喜び、「どうやったの」などと問いかけるのもよいでしょう。過程を振り返ることで、新たな挑戦につながります。
関わり方を工夫して子どもの「考える力」を伸ばそう

「考える力」は、子どもの学習意欲の向上や、円滑な人間関係の構築のために、重要な役割を果たす要素です。
その力を養うためには、保護者の関わり方が重要になってきます。
子どもが自分で考え、間違いを恐れずに試行錯誤できるような環境を整えて、成長をサポートしてあげましょう。
子どもが主体的に考える力を身に付けられるよう、ぜひ、本記事を参考にしてください、

スマホ・キッズケータイ


