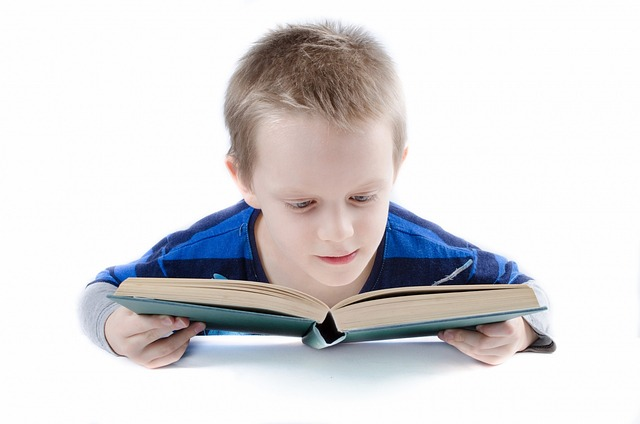早生まれが損といわれる3つの理由とは?メリットや遅生まれとの違いも解説

早生まれは損と聞いたことはないでしょうか。
子どもの生まれた日について、このように伝えられても、なぜそういわれるのか、よくわからないという方もいるでしょう。
この記事でわかること
・早生まれと遅生まれの定義
・早生まれは損といわれるのはなぜか
・早生まれのメリット
・早生まれの子どもを育てる際の心構え
早生まれの子どもが持たれやすいイメージを理解することで、将来的に早生まれの子どもが置かれる可能性がある状況を把握できます。そして、子どものことをより深く理解し、能力を伸ばすようサポートしていけるでしょう。
早生まれが不利といわれる理由について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
記事のまとめ
- 早生まれの定義と遅生まれとの違いについて、法律や入学時期の影響を基に詳しく解説している。
- 早生まれのデメリットとして、学力や体力差、保活への影響、児童手当の支給期間の短縮が挙げられている。
- 早生まれのメリットには、早期教育の開始、生涯賃金の増加、成長面での刺激を受ける環境があることが紹介されている。
早生まれの定義とは?
「早生まれ」とは、元日(1月1日)~4月1日までの間に生まれたこと、または生まれた人を表す言葉です。このような呼称ができたのは、この期間に生まれた子どもが、それ以降に生まれた子どもたちよりも早い月齢で小学校に入学するためです。
日本では、「学校教育法施行規則」の第五十九条により、小学校のはじまりは4月1日からと決められています。
そのため、元日~4月1日までに生まれた子どもは、4月2日以降に生まれた子どもよりも、約1年早く小学校へ入学することになります。
出典:学校教育法施行規則 第五十九条|e-Gov法令検索サイト
早生まれと遅生まれの違い
「遅生まれ」とは、4月2日以降に生まれたこと、または生まれた人を表す言葉です。
同じ年に生まれていても、「早生まれ」「遅生まれ」と区別されるのは、誕生日が子どもの小学校への入学時期に影響するためです。
早生まれの子どもの場合、6歳になった年の4月に小学校へ入学しますが、4月2日以降に生まれた子どもは、6歳になった翌年の4月に、小学校へ入学することになります。
そのため、同じ学年の子どもであっても、約1年近く年齢が異なる場合があるでしょう。
4月1日と2日で学年が変わる理由
同じ年の4月1日と4月2日生まれの子どもで学年が異なるのは、法律によって定められている、年齢の数え方に起因するものです。
学校教育法における年齢の数え方には、「年齢計算ニ関スル法律」の「生まれた日を年齢の1日目として数える」という考え方が適用されています。
そのため、4月1日生まれの子どもは前日の3月31日に満6歳を迎える計算となり、誕生日当日は、6歳の1日目と数えられます。
学校教育法では、小学校がはじまるのは4月1日と定められているため、この誕生日の子どもは、早生まれの子どもと同じ学年に区分されるのが一般的です。
出典:4. 4月1日生まれの児童生徒の学年について|文部科学省
出典:明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)|e-Gov法令検索サイト
早生まれは損といわれる3つの理由

遅生まれの子どもと比較して、早生まれの子どもは、さまざまな面で不利になるといわれがちです。
これは、同じ学年の子どもでも、生まれ月の違いから、最大で約1年の月齢差が生まれることが原因でしょう。
また、この差によって子どもたちの成長度合が変わると考える人もいるため、それがそのまま、早生まれの子どものイメージにつながっているといえます。
ここでは、早生まれの子どもが損といわれる、3つの理由を見ていきましょう。
学力や体力の差が気になる
小学校に入学したあとは、一つのクラスに、6歳11か月の子どももいれば、6歳0か月の子どももいるというように、年齢差がある子どもたちが一緒に生活するようになります。
一般的には、この年齢差が子どもの成長にも影響を与えると考えられているため、早生まれは損といわれています。
特に低学年のうちは、遅生まれの子どもほど成績がよい傾向があり、体格や体力面にも差が見られるため、早生まれの子どもは不利になりやすいでしょう。
ただし、学力については、年齢が上がっていくにつれて差が縮まる傾向にあるため、過剰に心配する必要はないでしょう。
一方、体格や体力の方は、生まれた時期の違いによる影響が長く続くと考えられています。
保活へ影響が出る
早生まれの子どもの場合、生まれ月によっては「保活(子どもを保育園に入れるための準備)」をはじめるタイミングが計りにくくなる可能性があります。
たとえば、子どもを0歳児クラスに入園させたいと思っていても、誕生日が2月4日以降だった場合、4月の入学には間に合わないでしょう。
その理由は、労働基準法で、出産後8週間は女性の就労が禁止されているためです。この期間は、母親が育児に専念しているとみなされ、保育園に子どもを預ける必要がないと判断されるため、基本的に認可保育園へは預けられません。
上記の理由で、0歳児クラスに入園できなかった子どもは、翌年の1歳児クラスへ入園することになるため、競争率が高くなります。
ただし、早生まれの場合でも入園時期をずらしたり、認可外保育園を利用したりするなどの対策で、保活への影響を減らすことは可能です。
出典:育児休業中に保育園に預けることはできるのですか?|東村山市
児童手当の支給期間が短くなる
早生まれの子どもは、「児童手当」の支給期間が短くなることも、損といわれてしまう理由でしょう。
児童手当とは、児童の生活の安定や健全な育成を目的として、各自治体から支給される手当です。その受給期間は、0歳~18歳の誕生日以降、最初の3月31日までとなっています。
たとえば、5月に生まれた子どもであれば、18歳の誕生日を迎えたあと、翌年の3月31日まで児童手当を受給できます。
一方、早生まれの子どもの場合、18歳になってから約2~3か月で受給期間満了日を迎えます。そのため、遅生まれの子どもと比較して、児童手当の総支給額は少なくなるでしょう。
早生まれならではのメリット3つ

早生まれの子どもの場合、学力や体力で、ほかの子どもと同じようにはいかない可能性があります。
しかし、勉強や就職に関して、遅生まれの子どもよりも早い時期から取組めるなど、結果的にプラスに働くケースもあるでしょう。
ここでは、早生まれの子どもが得られるメリットについて紹介します。以下に挙げる内容を参考に、早生まれならではの利点を把握しておきましょう。
早く教育がはじまる
幼稚園に入園する場合、早生まれの子どもは、遅生まれの子どもよりも早い時期に入園することになります。
そのため、より幼い年齢から教育をはじめられることは、早生まれの子どものメリットといえるでしょう。
幼稚園では、先生や同じ学年の友達から、お着替えやお片付けなどを教えてもらえるため、ほかの子どもよりも早く、身の回りのことができるようになります。
先生も、早生まれの子どもの扱いに慣れているため、適切に対応してくれるでしょう。
生涯賃金を多く受け取れる
仕事の定年は誕生日を基準にしているため、同じ条件で働いた場合、早生まれの人の方が生涯賃金が多くなります。これは、同じ年に入社した人でも、早生まれの人は遅生まれの人よりも誕生日があとになり、定年を迎える時期が遅いためです。
また、早生まれの人の方が働く期間も長くなることから、退職金の算定基準に勤続年数を用いている企業では、退職金が少し多くなる可能性があります。
遅生まれの友達から刺激をもらえる
早生まれと遅生まれでは、年齢が幼いほど成長や発達におよぼす影響が大きいとされています。体格や学力などで、遅生まれの子どもたちと比較すると、かなり不利な状況に置かれてしまう場合もあるでしょう。
しかし、そのような状況でも、同学年の子どもたちと競い合い、さまざまな刺激を受けることで、向上心のある努力家に育つ可能性があります。
早生まれの子を育てるときの心構え

早生まれで生まれた子どもは、同じ学年でも、約1年近く成長の早い子どもたちと一緒に過ごすことになります。
そのため、これまでは特に気に留めていなかったことでも、ほかの子どもとの差が気になってしまう場合もあるでしょう。
ここからは、早生まれの子どもへの対応で、心得ておきたいことをいくつか紹介します。ぜひ、子どもに接する際の参考にしてみてください。
必要なフォローをする
子育てで大切なのは、生まれ月を気にすることよりも、子どもにとって必要なことは何かを考え、それに合う対応をすることです。
「子どもが早生まれだから成長が遅い」と決めつけるのではなく、子ども自身の成長や発達を見守ってあげましょう。
ときには、遅生まれの子どもについてくために必要なサポートを行うなど、子どもの意思を尊重しながら、心地よい環境を整えることが大切です。
ほかの子と過剰に比較しない
早生まれの子どもの発達や成長について、ほかの子どもたちと比較することは好ましくありません。
同級生と比較してできないことがあったとしても、叱るのはやめましょう。その理由は、保護者に叱られることで、子どもが劣等感を抱いてしまう可能性があるためです。
そのようなことを避けるためにも、「遅生まれの子どもと比べてできないこと」ではなく、「子ども自身がどう変わってきているか」に目を向けるようにしてください。
できるようになったことを認めて、きちんと成長できていることを喜ぶようにしましょう。
早生まれだからと心配せず、子どもと向き合おう

早生まれであることが、子どもの成長や発達、保活などに影響する可能性があることは事実です。
しかし、成長していくなかで、遅生まれの子どもとの差は縮まっていくため、過剰に心配する必要はないでしょう。
逆に、早生まれならではのメリットを得られる可能性もあるため、「早生まれは不利」と決めつけないことが大切です。
本記事では、早生まれの子どものメリット・デメリットについて紹介しました。
子育てで大切なことは、生まれ月を気にすることではなく、子ども自身の成長を見てあげることです。
ポジティブな気持ちで子どもと向き合うために、ぜひ、本記事を参考にしてください。