回文とはどんな言葉?作り方やルール、有名な回文10個をご紹介

回文とはどのような言葉遊びかご存知でしょうか。
言葉遊びをすることで、お子さまの言語能力が向上すると聞いたことはあっても、実際にどのように取り組めばよいかわからず、お困りの方もいるでしょう。
この記事でわかること
・回文とはどういうものなのか
・回文の作り方のコツ
・回文作りのルール
・お子さまと一緒に取り組むメリット
回文について理解することで、お子さまの年齢に合わせて難易度を工夫しながら一緒に回文作りを楽しめます。その結果、効果的にお子さまの言語能力を向上させることができるでしょう。
回文について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
記事のまとめ
- 回文は、上から読んでも下から読んでも同じ音になる言葉や文章で、世代を問わず楽しめる。
- 回文作りは語彙力や思考力向上に役立ち、親子で取り組むとコミュニケーションの促進にもなる。
- ルールやコツを工夫しながら回文を作ることで、言葉遊びの楽しさと学びを両立できる。
回文とは何か
「回文(かいぶん)」とは、上から読んでも下から読んでも、同じ音になる単語や文章のことをさします。
古くから親しまれている言葉遊びの一つで、子どもから高齢者まで世代を問わず楽しめます。小学校の国語の授業にも取り入れられており「竹やぶ焼けた(たけやぶやけた)」などは、有名でしょう。
英語の回文もある
回文は英語にもあります。英語では「Palindrome(パリンドローム)」とよばれ、日本と同じく古くから親しまれてきた言葉遊びです。
パリンドロームには「Madam, I’m Adam.」のように、アルファベット単位で逆から読んでも意味が通るようになっているものと、単語単位で成立するものがあります。単語単位の回文は、日本語の回文とは少し異なるスタイルといえるでしょう。
単語単位の回文の例は、以下のようなものとなります。
・King, are you glad you are king?
・Fall leaves after leaves fall.
・You can cage a swallow, can’t you, but you can’t swallow a cage, can you?
回文を作るときは身の回りの言葉を逆さに読んでみる
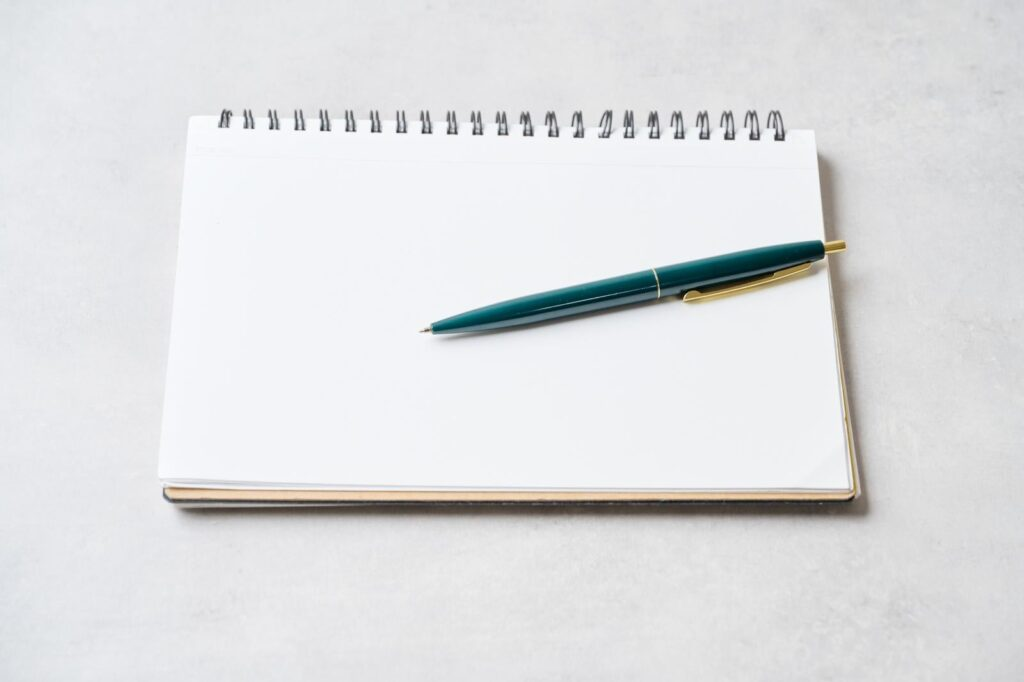
回文には、自分でオリジナルの回文を作る楽しさもあります。回文を作る場合は、無理に「逆から読んでも意味が通る言葉」を探そうとせずに、まず身の回りにあるものの名前や思いついた言葉を逆から読んでみましょう。
単独では意味がないように思う言葉でも、並びを入れ替えてみたり重複した文字を消してみたりすることで、簡単にオリジナルの回文を作ることができます。
最初は、2~4文字の短い単語からはじめてみることをおすすめします。慣れてきたら複数の言葉を組み合わせた、長い回文作りに挑戦してみてください。
回文を作る際のルール
回文は、逆から読んでも同じ音であることに加えて「意味が通っている」ものが多いでしょう。また「が」などの濁音や「ぱ」などの半濁音は、変更不可ということもあれば「ハート」に含まれた長音符は「はあと」に読み替え可能としていることもあります。
このように、本来回文には明確なルールはありません。
どのようなルールを設定するかによって、回文の作成難易度は変わります。ルールを自由に定めることができる点は、多くの世代で回文作りが親しまれるポイントの一つでしょう。
子どもと回文を作るメリット

回文作りに取組むことで、多くの言葉を知るきっかけになり、お子さまの語彙力を向上させる効果が期待できます。また、言葉と言葉のつなげ方を試行錯誤することで、接続詞の使い方や思考力を身に付けるよい機会にもなるでしょう。
そのため、ぜひ、お子さまと一緒に回文作りに挑戦してみてください。
お子さまが楽しく回文作りに取組めるように、あまり厳しいルールは設けないようにすることが大切です。
回文になっている単語10選

言葉の組み合わせ方を工夫することで、回文を簡単に作ることができます。しかし、小さなお子さまにとっては難しく感じてしまう場合もあるでしょう。
お子さまが上手く回文を作れないときは、まずは身近にある「回文になっている単語」を親子で一緒に探してみることからはじめてみましょう。逆から読んでも意味が通る単語は意外に多いので、お子さまも飽きることなく言葉探しをすることができます。
回文になっている単語は、以下のようなものがあります。
・ルール
・アジア
・子猫(こねこ)
・キツツキ
・奇跡(きせき)
・痛い(いたい)
・目覚め(めざめ)
・理科係(りかがかり)
・新聞紙(しんぶんし)
・キツネ憑き(きつねつき)
6文字以上10文字未満の回文5選
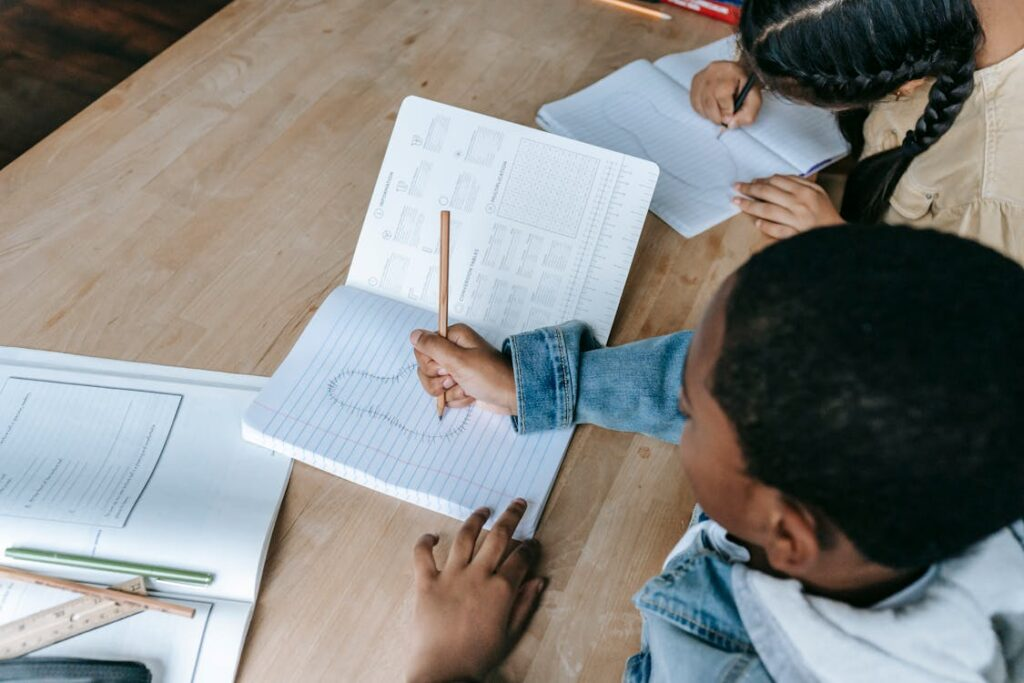
小学生以上のお子さまと一緒に楽しむ場合は、6文字以上の回文作りにチャレンジしてみましょう。
6文字以上にするためには、複数の単語を組み合わせる必要があります。文字数が増えるほど、逆から読むことを意識しなければ上手な回文にはならないので、思考力や発想力が鍛えられるでしょう。
以下の回文は、6文字以上10文字未満の例です。
・池と時計(いけととけい)
・右手バテ気味(みぎてばてぎみ)
・かっこいい国歌(かっこいいこっか)
・ゾウ買いたい!買うぞ!(ぞうかいたいかうぞ)
・夜すき焼きするよ(よるすきやきするよ)
子どもと一緒に回文を作って遊んでみよう

回文になっている言葉を探したり、自分たちでオリジナルの回文を作ったりすることで、お子さまが言葉遊びの楽しさを感じられ、周囲とのコミュニケーションもはかどるでしょう。
そして、ゲーム感覚で回文に慣れていけば、自然と語彙力が高まっていき、思考力や発想力の向上も見込めます。
この記事で紹介したルールやコツを参考にして、お子さまと回文作りを楽しんでみてください。

