子どもの理解力は将来に影響する?3歳の子どもの目安と向上させる方法をご紹介

子育てをする上で、子どもの理解力を鍛えることは大切だと聞いたことはないでしょうか。
しかし、理解力を向上させる具体的な方法がわからないという方もいるでしょう。
この記事でわかること
・理解力って何?
・3歳の子どもの理解力
・理解力を向上させる方法
子どもの理解力について知ることで、社会で求められている理解力とはどのようなものかがわかります。また、より理解力の高い子どもに育てていけるでしょう。
子どもの理解力の必要性や、向上させる方法について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
記事のまとめ
- 理解力は文章や話の内容を把握する能力で、読解力や聞く力とは異なる役割を持つ力である。
- 3歳児の理解力の目安には数を数える、色や形を認識する、なぜと質問する行動が含まれる。
- 普段の生活で数字や色を意識させ、教育アプリを活用することで理解力を効率的に高められる。
理解力とはどんな力か
「理解力」とは、書かれている文章や、聞いた話の内容を理解する能力です。
理解力は、読解力や聞く力とはまた別の能力です。読解力は文章を読むために必要な能力で、聞く力は人の話を聞くために必要になります。
しかし理解力がなければ、文章を読んだり会話を聞いたりすることはできても、内容についてはわからないままでおわってしまうでしょう。
3歳児の理解力の目安
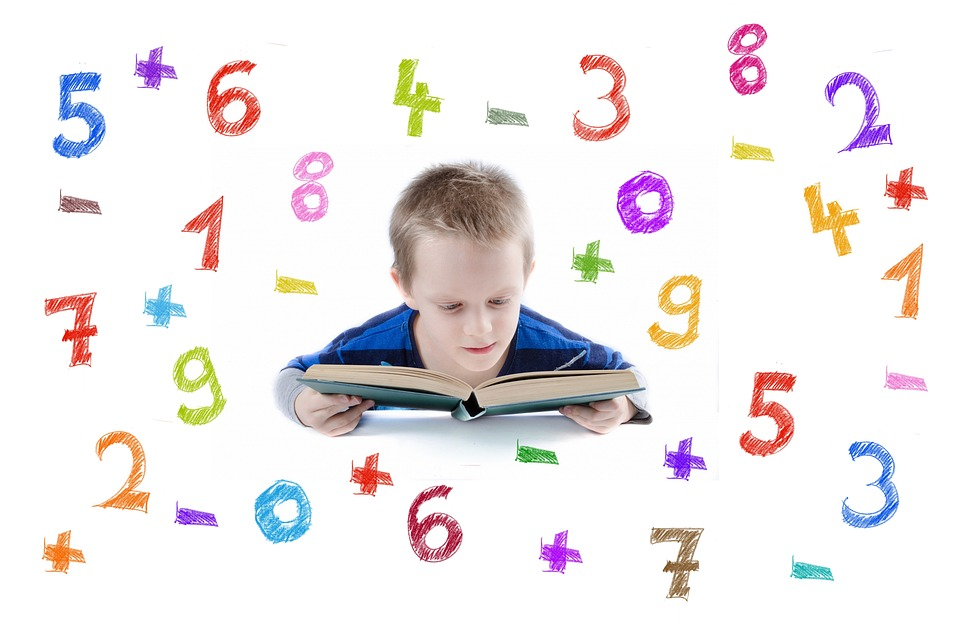
3歳になると、子どもはさまざまなことを自分の力でできるようになっているでしょう。子どもの普段の様子を見ることで、子どもの理解力がどの程度成長しているかを把握できます。
ここからは、3歳の子どもに求められる理解力の目安を紹介します。紹介している項目でこなせることが多いほど、子どもの理解力は成長しているといえるでしょう。
数を数えられる
3歳の子どもであれば、数を理解し、小さな数字を順番に数えられると理解力があるといえるでしょう。また、大人が子どもに「3と5ではどちらが大きい数字か」といった質問をして、正解を答えられることも目安になります。
おやつが2つあった場合に、2人で1つずつわけることはできるでしょう。
ハサミが使える
3歳の子どもにハサミの使い方や使うときのルールを説明し、それらを理解した上で子どもがハサミを使えていれば、理解力があるでしょう。
紙とハサミを渡して、子どもがハサミで紙を切ることが理解力の目安です。その際、紙を直線に沿って切る必要はありません。
理解力が低い子どもの場合は、ハサミの使い方や使う上でのルールを教えてもどのようにすればよいかわからず、ハサミを上手に使えないでしょう。
色と形が認識できる
色を指差したときに、3歳の子どもがその色の名前を答えられることや、図形を見せてどのような図形か答えられることが理解力の目安です。また子どもが三角や四角など、描きたいと思った図形をそのとおりに描くことができるとよいでしょう。
これらのことができれば、色と色の名前、図形の名前と形が子どものなかではっきり結びつき、理解できている証になります。
子どもが色を認識できるようになる頃には、色の好みも出てきます。好きな色の服ばかり着る子どもや、絵を描くときに特定の色ばかり使うような子どもが出てくるでしょう。
「なぜ」という質問が増える
3歳になった子どもから、「なぜ」や「どうして」という質問が出てきていれば、年齢に合った理解力があるという目安になります。
3歳を迎える頃までは、一方的に保護者が子どもに教えることが多いでしょう。しかし子どもが成長すると、子どもから保護者への質問が増えてきます。このため、2~4歳頃の子どもは「なぜなぜ期」と呼ばれています。
なぜやどうしてと質問してくる子どもに対して、保護者は気持ちに寄り添い、きちんと対応することで、子どもの思考力やコミュニケーション力を伸ばせるでしょう。
理解力が向上することによるメリット
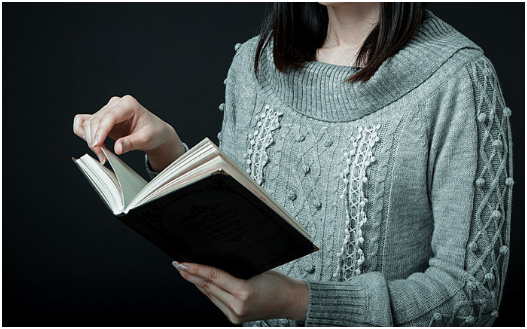
ここでは、子どもの理解力を向上させるとどのようなメリットがあるかを紹介します。
子どもの理解力が上がるメリットの1つは、子どもの勉強がはかどることです。たとえば、文章を理解できるようになることで国語の成績が上がる可能性があるでしょう。文章の理解力は、国語だけでなく数学やほかの教科でも必要になります。
また、勉強以外にも理解力の高さは役立ちます。子どもが将来、大人になってからも得られる理解力のメリットについては、こちらの内容を参考にしてみてください。
コミュニケーションがスムーズに取れるようになる
子どもに理解力があれば、相手の話し方に左右されず、何がいいたいのか推測することが可能です。
また会話のなかで相手の気持ちを想像し、子ども自身がどのように振る舞えばよいかわかるでしょう。子どもが相手に対して、適切な対応をしていくことで、スムーズなコミュニケーションが取れます。
将来仕事をスムーズに進められる
子どもが大人になったときに、仕事で理解力の高さを活かし、自分の状況を正しく把握できたり、状況に合わせて対応したりできます。
単独で仕事をするときだけでなく、チームを組んで仕事をする際にも、理解力の高さが役立つでしょう。
また、クライアントから話を聞くようなときに、相手が何を望んでいるのか、ニーズを正しく把握できます。仕事について説明する際に、自分の言葉で上手に説明することも可能です。
理解力を向上させる方法

ここでは、子どもの理解力を向上させるための方法を紹介します。
子どもの理解力が低い場合でも、保護者の対策によって高めていくことが可能です。
子どもの理解力を高めるために、普段から気をつけたい行動や、遊びのなかで取り入れていった方がよいことなどを把握して、保護者がサポートしてあげましょう。
普段の生活のなかで数字を意識させる
子どもの数字への理解が低い場合は、日常生活のなかで保護者が数字を何度も使い、意識させるようにしましょう。
たとえば、保護者が子どもと一緒にままごとやごっこ遊びをしているときに「りんごはいくつある?」と聞いて数えさせてみてください。買物のときには、「おやつを2つ選んでね」といったように個数を伝えて実行させましょう。
また、食事のときも「今日はトマトが3つあるよ」と保護者が子どもに伝えることで、実際の個数と数字を結びつけるようにしていきます。
子どもとたくさんコミュニケーションを取る
子どもと積極的にコミュニケーションを取って、どのように人と話せばよいかお手本を見せましょう。
そのためには、保護者が子どもの話をきちんと聞いてあげることが大切です。忙しいなかでも、子どもを理解するためにできるだけ話を聞く時間を取ってあげましょう。
また子どもに話すときは、わかりやすい言葉にします。3歳の子どもはまだ難しい言葉の意味を理解できないため、短く話すことも意識しましょう。
理由を説明しながら叱る
子どもを叱るときは、保護者は頭ごなしに叱るのではなく、何が悪かったのか理由を説明して叱りましょう。
保護者がきちんと理由を説明することで、子どもは何がいけなかったか、どうすればよいかを考えるようになり、子どもの理解力向上にもつながります。
また、子どもがしてはいけないことをしたときに、保護者が「~されて悲しかったよ」という叱り方をすることで、感受性も育てられるでしょう。
色を使う遊びをする
子どもの色への理解が足りていない場合は、遊びのなかで色を使うようにしましょう。
子どもと一緒に、さまざまな色で塗られている積み木や、塗り絵やお絵描きなどで遊んでみてください。子どもが色には多くの種類があることや、それぞれの色の名前などを知る機会になります。
また、子どもに好きな色がある場合は、好きな色がどこに使われているのか、どのような色かなどの情報を保護者が教えていきましょう。好きな色に関する内容であれば、子どもが早く理解してくれる可能性があります。
普段の生活のなかで理解度の向上を図ろう

子どもに理解力があることは、勉強やほかの子どもたちとのコミュニケーション、将来の仕事によい影響を与えます。そのため、子どもが幼いうちから育てておきたい能力でしょう。
3歳頃の子どもの理解力が育っているかどうかは、子どもが数や色を理解しているか、ハサミを使えるかなどの項目で判断可能です。
もし子どもの理解力が不足していた場合は、親子でコミュニケーションをとり、数や色を日常のなかで意識させたり、遊びに取り入れたりしていきましょう。


