中学生の受験勉強は何からすればいい?時期別の対策や効率よく進める方法をご紹介!
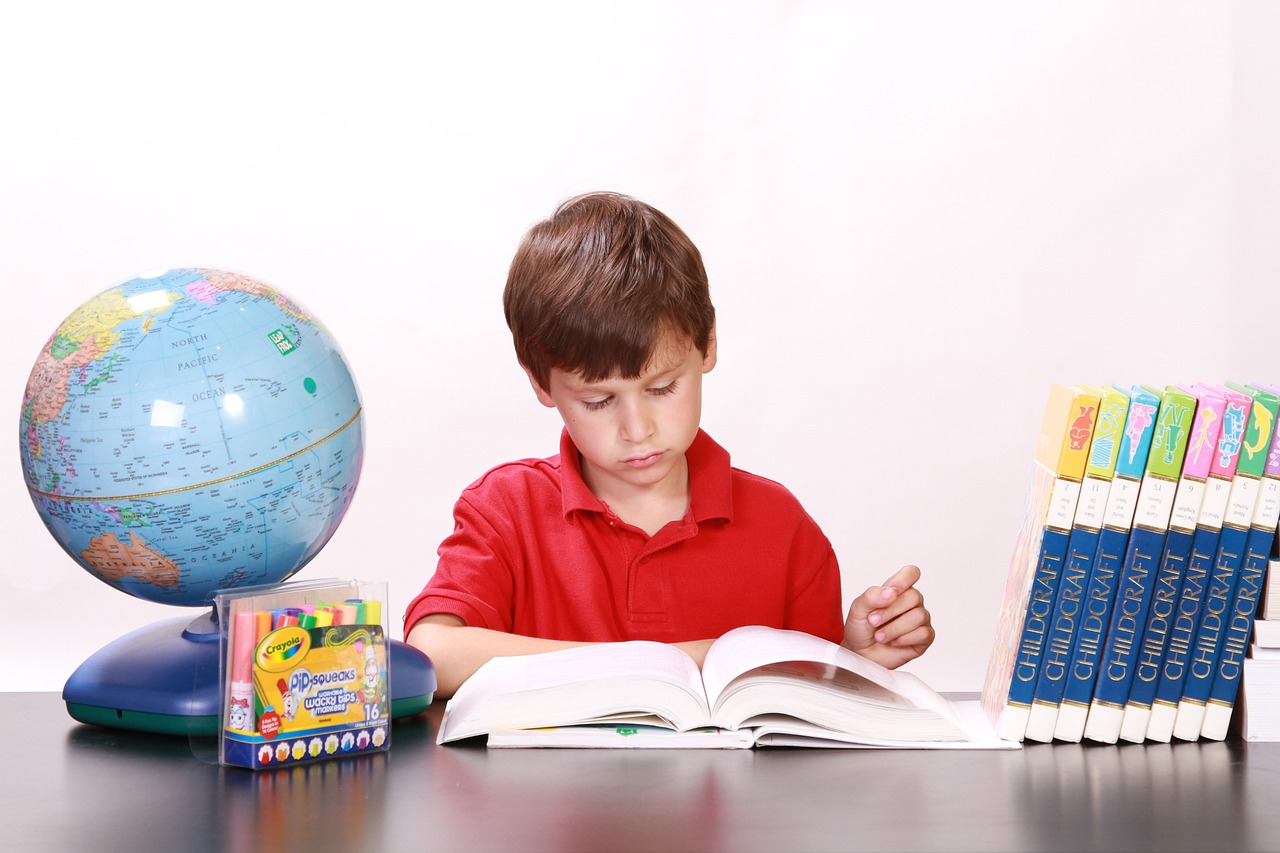
高校の受験勉強は何から取組めばいいかご存知でしょうか。
中学生のお子さまを持つ保護者のなかには、お子さまの将来を考え、できるだけいい高校に進学してほしいという方もいるのではないでしょうか。
この記事でわかること
・中学生の受験対策は何からはじめればいいか
・高校受験に合格するための効率的な学習方法
・時期別の学習内容
時期別の学習内容や勉強方法を知ることで、受験に悩むお子さまの手助けができます。また、お子さまが志望する高校への合格に一歩近付けるでしょう。
高校受験の勉強方法について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
記事のまとめ
- 高校受験対策は、中2春から基礎固めを行い、中3夏は総復習と苦手克服、中3冬以降は過去問演習を重視する。
- 内申点向上には定期テスト対策が重要であり、先取り学習や日々の授業理解が高得点獲得につながる。
- 学習塾や隙間時間を活用し、効率よく勉強を進めることで、志望校合格に近づける対策が可能だ。
中学生の受験勉強は何からすればいい?
高校受験を見据えて受験勉強をはじめたいものの、どこから手をつければいいのかわからず悩んでいる中学生をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。
高校受験は内申点や調査書が重視されます。そのため、早い段階から定期テスト対策や生活態度などを意識する必要があるでしょう。
ここからは高校受験に向けて、中2の春以降の具体的な勉強内容を確認していきましょう。
中2の春は中1の学習内容を総復習をする
中2の春から高校受験の勉強をはじめる場合、中1で学んだ範囲の復習に取組みましょう。
中2で学ぶ内容は中1で学習した内容の応用であり、学習をスムーズに行うためにも中1で学んだ基礎を固めておく必要があります。
中2は部活動で忙しくなる場合が多く、家庭で学習する時間の確保が難しくなる可能性があります。中1の学習内容を固めておくと、授業の内容を理解しやすくなり、部活で疲れたあとの学習時間を短縮することにもつながるでしょう。
中2の春の家庭で学習する時間としては、1時間半~2時間程度が一般的といわれています。難関校をめざす場合は、2時間~3時間程度が目安です。
中2の夏以降は定期テスト対策をする
中2の夏以降は、調査書や内申点対策として、定期テスト勉強や先取り学習を進めまfしょう。
高校受験では調査書や内申書などで、中学生活での態度を重視する高校も多数あります。そのため、定期テスト対策は欠かせないでしょう。
定期テストで高得点を獲得するためには、日々の授業を素早く理解することが重要です。
先取り学習を進めておくと、学校の授業が復習の場となり、理解が深まります。また、予習の段階でわからない点があれば、授業中に解決できるため、学習内容を効率よく定着させることができるでしょう。
中2の冬休みから中3の夏休み前までに各教科の基礎をおさらいする
中3の夏休み前までに、各教科の基礎習得を心がけましょう。
中2の冬休みから中3の夏休み前は、多くの中学生が部活動に勤しむ時期であり、勉強時間の確保が難しい場合が多いです。そのため、毎日30分だけ勉強時間を確保するなど、まずは学習習慣から身に付けましょう。
学習内容では、今までの総復習と苦手の克服をメインにし、高校受験問題を解くための基礎を固めておく必要があります。たとえば、英語であれば単語を覚えたり、数学であれば基礎的な計算問題を解いたりすることが挙げられます。
ただし、基礎問題だけにならないようにすることも大切です。得意分野については、応用問題にもチャレンジしてみましょう。
中3の夏休み期間中は総復習や苦手克服にあてる
中3の夏休みは中1・2の総復習をしながら、弱点克服をめざしましょう。夏休みは勉強時間を確保できる傾向にあるため、時間のかかる弱点克服に取組むことが可能です。
ある程度基礎問題を解けるようになったという方は、教科書やワークにある応用問題に挑戦してみるのもいいでしょう。
中3の秋から冬休みは志望校に合わせて問題集を反復する
冬休みまでの期間は、志望校に応じた問題集を使用し、出題されやすい分野を重点的に繰り返し学習しましょう。このときに使用する問題集は標準レベルのものを使用します。
方程式が多く出題される高校を受験する場合は、方程式・計算問題を中心に収録されている参考書で対応できます。また、証明問題や記述問題が多く出題される場合は、応用レベルの問題集を使用しましょう。
難関校を受験する場合は、志望校別の受験対策の問題集を使用して学習する必要があります。
中3の冬休み明け以降は過去問題で受験対策をする
中3の冬休み以降は、受験本番を想定して過去問演習をしましょう。実際に、過去問題に取組むことで、志望校のレベル感を把握できます。
志望校のレベルに応じた過去問題を準備し、必ず一度解いてみましょう。
過去問題を解くなかで、わからなかった問題や難しかった問題があれば、その分野を重点的に復習し定着させておく必要があります。
受験直前期は暗記科目に注力する
受験直前期は、応用問題や演習問題ではなく、得点アップに直結する暗記科目を強化することがおすすめです。
ただし、用語を覚えただけでは点数獲得につながらないため、過去問題を使用して、反復練習をすることも忘れないようにしましょう。
効率よく高校受験を進めるには?

受験勉強は先を見据えたスケジュールを立て、効率よく学習を進めていくことが重要です。
そのために、学習塾に通うといった選択も出てくるでしょう。しかし、塾に通ったからといって、必ず成績が上がるわけではなく、各自の努力によって成果は変わってきます。
そこで、志望校合格に向けてどのように勉強を進めるといいかを解説します。
学習塾で学力を補う
学習塾に通うと、志望校のレベルに応じたスケジュールを作成してもらうこともできます。わからない問題をすぐに先生に質問できるといった点から、より効率的に受験勉強を進めることが可能です。
学習塾に通うタイミングとしては、より早い方がいいとされています。具体的には、受験生本人が受験勉強に対して不安を感じ、塾に行った方がいいか悩む時期が目安です。
いきなり通塾することに不安を抱く場合は、体験授業を実施している学習塾もあるため、体験してから検討してみるといいでしょう。
オリジナルの過去問ノートを作る
志望校合格に欠かせない苦手克服のために、間違えた問題を記載したオリジナルの過去問ノートを作成することがおすすめです。
具体的な作成方法としては、過去問を解いた際に間違えた問題を過去問ノートに記録し、翌日に再度問題を解きます。問題を解く際は、別のノートを用意し、オリジナルの過去問には直接記入しないようにしましょう。
オリジナルの過去問は、最低3回は解き直し、間違えた問題と正解した問題に印をつけておくと、できるようになった問題がすぐにわかり、達成感にもつながります。
過去問ノートを作成しておくと、自ずと自身の苦手問題に繰り返し取組むことができ、志望校合格への近道となるでしょう。
隙間時間を活用して無理なく学習を進める
隙間時間を上手く活用して学習するようにしましょう。隙間時間は登下校、お風呂、休憩時間など想像以上に多くあります。人によっては、1日4時間程度あるともいわれています。
隙間時間での学習は、すぐに勉強をはじめられるように、暗記科目などペンを使用しないものがおすすめです。
十分な受験対策で高校受験を突破しよう

中学生の高校受験対策は、時期ごとに取組むべき内容が異なります。中2の春は基礎固め、中3の夏は総復習や苦手克服を重視し、冬以降は過去問を活用した実践練習が鍵です。
また、学習塾の活用や隙間時間を活かした効率的な学習も効果的でしょう。早めの計画と適切な対策で志望校合格に近付きます。
高校受験の準備にお悩みの方はぜひ本記事を参考にし、受験勉強をはじめてみましょう。


