子どもにスマホを持たせた際に、トラブルが起こる可能性があることをご存じでしょうか。
子どものスマホトラブルの事例を聞いて、子どもにスマホを持たせるべきか悩む方もいるでしょう。
子どもに実際に起こったスマホトラブルを知ることで、子どものスマホ利用にひそむリスクを把握できます。そして、スマホトラブルを避けるための対策を講じていけるでしょう。
子どもに起こりうるスマホトラブルや、スマホトラブルの対策方法について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
記事のまとめ
- 子どものスマホ利用によるトラブル事例として、詐欺や課金トラブル、SNSいじめ、個人情報漏洩がある。
- 対策として、ネットリテラシーを親子で学び、利用ルール設定やフィルタリング機能の活用が推奨される。
- 相談先として、消費者ホットラインや行政窓口、NPOがあり、早めの相談が問題解決につながる。
子どもに起こるスマホトラブル事例
近年では、子どものスマホ利用が増えています。低年齢層では親と共用のスマホを使用していても、小学生になると子ども専用で持つ子どもが増えるでしょう。
しかし、子どもがスマホを利用することには、さまざまなトラブルに巻き込まれるリスクがあります。それは金銭的なトラブルだったり、子ども同士のトラブルだったり、大人が関与するトラブルもあるでしょう。
ここでは、子どもに起こる可能性のあるトラブルを6つ紹介します。
フィッシング詐欺やクリック詐欺
子どもがスマホでクリックしてしまうことで起こるスマホトラブルには「フィッシング詐欺」「クリック詐欺」があります。
フィッシング詐欺はURLを記載したメールを送り付け、そのURLをクリックさせることで個人情報を取得する詐欺です。
そしてクリック詐欺は、WebサイトやメールなどにあるURLをクリックさせ、その結果高額な費用が発生したと錯覚させ、支払いを求める詐欺です。
課金による高額請求
子どもがスマホのアプリやゲームを利用している際、料金が発生することを理解せずに同意してしまうことで、高額請求のトラブルが起こることがあります
スマホのアプリやゲームは、無料ではじめられるものでも、途中で課金が必要になるものがあります。課金するたびに子どもが親に相談して、了解を得ていれば問題ないでしょう。
しかしなかには、子どもが無料だと勘違いして利用し続け、結果的に高額請求されてしまうケースも少なくありません。
SNSにおける誹謗中傷やいじめ
子どもはスマホでSNSを利用し、友達とコミュニケーションを取ることがありますが、その際に誹謗中傷やネットいじめが起こる場合があるでしょう。
SNSではささいなことで、トラブルが発生する可能性があります。知らないうちに子どもの悪口が書き込まれる、あるいは子ども自身が不適切な投稿をしてしまい、SNSで炎上するようなことも問題視されています。
SNS・出会い系サイトによる犯罪被害
SNSや出会い系サイトなどに登録し、出会った人と意気投合して一人で出かけてしまうと、犯罪被害にあう可能性があります。
たとえば、SNSや出会い系サイトでは別人を装い、実際に会ってみると全く違う人物だったということがあります。
SNSや出会い系を通じた出会いは、実際に顔を会わせる訳ではないので、本人のプロフィールどおりの人とは限りません。犯罪者が別人になりすましていることもあり得ます。
個人情報の漏洩
スマホを使って、子どもが簡単に写真や情報を投稿できるようになりましたが、その内容から個人が特定され、個人情報が漏洩するリスクがあります。
どの程度の情報が簡単に抜かれてしまうかというと、たとえばピースサインの写真を投稿すると、指紋がわかります。また自撮り写真を投稿しただけでも、外で撮影していた場合、瞳に映った景色から住所を特定されるようなこともあるでしょう。
著作権の侵害
子どもが著作権を意識せずに、勝手に他人の画像や動画などをSNSに投稿してしまった場合、著作権侵害を問われるおそれがあります。
子どもが日常的に見ているアニメや映画には、著作権があります。もし子どもが悪意なくアップロードやダウンロードを行った場合でも、著作権侵害になる可能性があるでしょう。
また、子どもがSNSで自身のプロフィールに他人や有名人の画像を使用してしまうと、肖像権侵害になることもあります。
出典:インターネットトラブル事例集(平成29年度版)|総務省
スマホトラブルを防ぐための対策

子どもにスマホを持たせると、連絡が取りやすくあんしんできるというメリットがあります。しかしその一方で、子どもにスマホを持たせることで、さまざまなトラブルにあうリスクが高まることも事実です。
子どもにスマホを持たせる際には、スマホトラブルを防ぐ対策を行っていくことが大切です。保護者が行える対策や親子でできる対策などがあるので、以下を参考に対策してみてください。
子どもと一緒にネットリテラシーについて学ぶ
スマホを利用するにあたり、以下に挙げた4つのネットリテラシーを親子で学び、身に付けていきましょう。
・個人情報が特定できるような投稿をしない
・真偽のわからない情報を拡散しない
・インターネット上の画像を勝手に利用しない
・匿名であることを過信しない
保護者にネットリテラシーがあっても、子どもになければトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあります。保護者がまずネットリテラシーを学び、その内容を子どもにわかりやすく教えてあげましょう。
利用しているアプリ・SNSを把握しておく
子どもにスマホを好きに使わせるのではなく、実際に何の機能を利用しているかをチェックしてください。特にSNSのアプリは、子どもがコミュニケーション手段として利用することが多いでしょう。
子どもが頻繁に利用しているアプリで何ができるかを確認し、将来起こりうるリスクを想定しておきましょう。
スマホ利用のルールを決める
子どもがスマホを利用するにあたって、使用上のルールを決めておきましょう。
保護者の知らないところで子どもがスマホを利用してしまうと、どれだけスマホを使用しているか把握することが困難になります。
子どもが何を目的としてスマホを利用するか、1日のうち何時間利用してよいか、どこで利用するかなどのルールを決めておけば、スマホトラブルの対策になるでしょう。
スマホトラブルを防ぐために使える機能
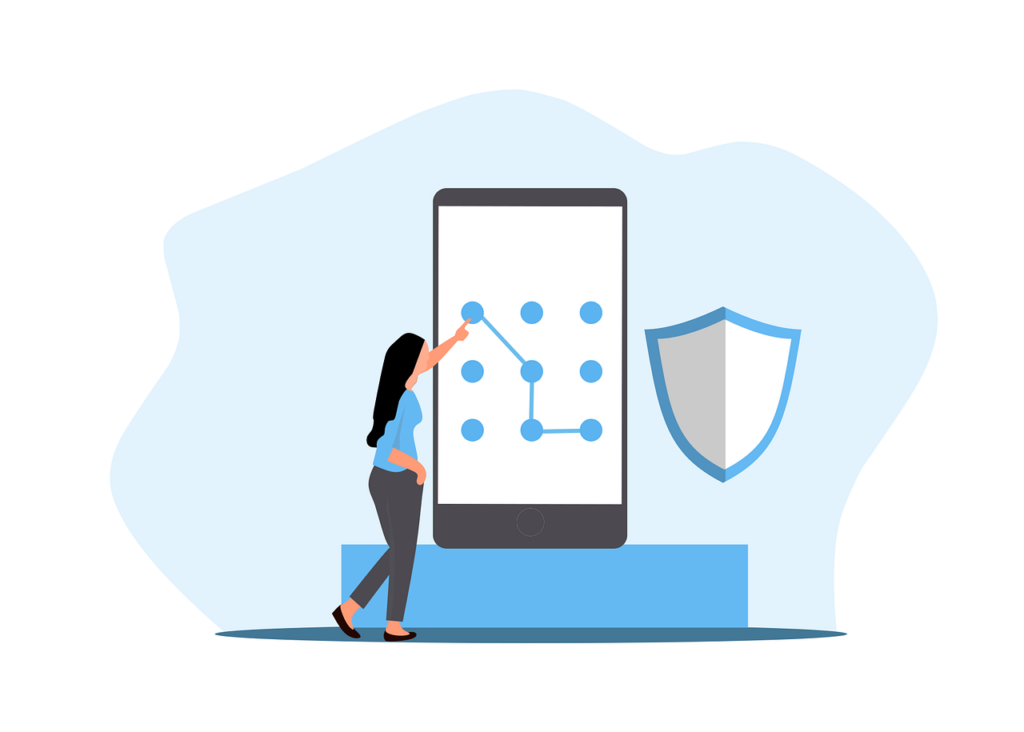
子どもに起こるスマホトラブルを防ぐための対策として、機能やサービスを利用することも可能です。
保護者があらかじめ、子どもに持たせるスマホにそれらを設定しておけば、子どもにあんしんしてスマホを利用させられるでしょう。以下では、主に2つの便利な機能について解説していきます。
フィルタリング機能
「フィルタリング機能」は、子どもがスマホからアクセスできるサイトやアプリを制限する機能のことです。
フィルタリング機能には、2種類あります。子どもにもあんしんして利用させられる、一定の基準を満たしたサイトのみにアクセス可能なホワイトリスト方式と、有害サイトへのアクセスを制限するブラックリスト方式です。
上記のほか、子どもの年齢に合わせてフィルタリングの範囲を変更するといった、フィルタリングサービスもあります。
ペアレンタルコントロール機能
「ペアレンタルコントロール機能」は、子どものスマホの利用状況を保護者が把握できる機能のことです。
ペアレンタルコントロール機能を使用すれば、子どもが何時間スマホを利用しているか、何のアプリを使用しているかといった情報を知ることができます。
また、ペアレンタルコントロール機能では、スマホの利用時間を制限することも可能です。アプリそのものの使用を許可もしくはブロック、さらには課金の可否を設定できるサービスもあります。
スマホトラブルが起きたときの相談先3選

親子でスマホトラブルに備えていても、意図せず巻き込まれてしまう可能性は否定できません。そのようなときは、お金を支払って解決しようとすることや、一人で悩みを抱えてしまうようなことはせず、誰かに相談することが大切です。
ここでは、スマホトラブルが起こったときの相談先を3つ紹介します。全国が対象の相談先や都道府県別の相談先があるので、相談しやすいところに電話してみてください。
消費者ホットライン(188)
消費者庁の「消費者ホットライン」では、電話することで、相談可能な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。全国から「188」で電話がつながります。
消費者ホットラインに向いている相談は、スマホ利用時に発生した不当な高額請求です。フィッシング詐欺やクリック詐欺などにあった際の相談先として、覚えておきましょう。
行政窓口・NPO
スマホトラブルにあったものの、どこに相談してよいかわからない場合や、気軽に相談したい場合は、行政窓口やNPO法人への相談もおすすめです。
子どもがスマホで嫌な目にあったとき、あるいは嫌な目にあっている人を見かけたときの相談先の候補は「こどもの人権110番」です。相談は、月曜日~金曜日の午前8:30分~午後5:15まで受け付けています。
また、子どもが気楽に相談したい場合は「チャイルドライン」が相談先になります。ちょっとしたことでも相談でき、チャットでの相談も可能です。
出典:いじめ などの電話相談窓口【こどもの人権110番】|法務省
出典:チャイルドライン|特定非営利活動法人 チャイルドライン支援センター
都道府県警察の相談窓口
「都道府県警察の少年相談窓口」は、スマホトラブルのなかでも、犯罪に巻き込まれた場合の相談先になります。
ネットでの誹謗中傷や個人情報が漏れて流布されたとき、詐欺に巻き込まれた場合や覚えのない高額請求にあった場合は、こちらへ相談するとよいでしょう。そのほか、自分の写真を他者に勝手に使用されたといったトラブルも相談可能です。
各都道府県で相談先が異なるので、お住まいの都道府県に確認してみてください。都道府県によっては、警察のホームページ内から相談できるところもあります。
十分な対策を行ってスマホトラブルを未然に防ぎましょう

子どもがスマホを所持するようになり、子どもがスマホトラブルに巻き込まれる事例が見受けられるようになりました。子どもがスマホ操作を誤って詐欺にあったり、意図せず高額課金したり、SNS上でのいじめに巻き込まれる可能性もあるでしょう。
スマホトラブルは、保護者だけでなく子ども自身でも気をつける必要があります。親子でネットリテラシーを身に付け、安全な機能やサービスを使用し、スマホトラブルを未然に防いでいきましょう。
また、もしスマホトラブルにあった際は、本記事の相談先を確認し、早めに相談するようにしてください。

