子どもにとって家庭学習は大切!家庭学習のメリットや学習方法をご紹介
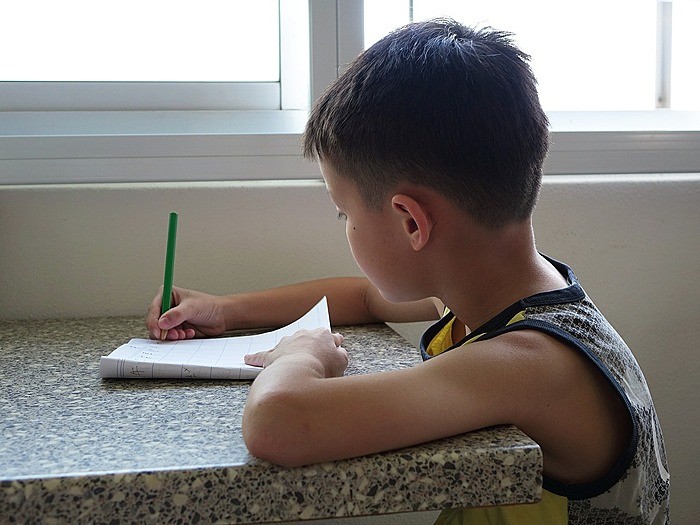
子どもの家庭学習について悩んでいる人はいませんか。この記事では、家庭学習の必要性とともに、家庭学習のメリットや学習方法、家庭学習を習慣化させるコツを紹介しています。子どもの家庭学習を支えたいと考えている人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
「子どもの家庭学習ってどうして大切なの?」
「家庭学習のメリットや学習方法を教えてほしい」
「家庭学習を習慣化させるコツや苦手な子の特徴ってある?」
このように、子どもの家庭学習について疑問や興味を持っている保護者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、子どもの家庭学習の大切さとともに、家庭学習のメリットや習慣化させるコツ、家庭学習が苦手な子の特徴や実際におすすめの学習方法を紹介しています。
この記事を読むことで、家庭学習の重要性や対策を把握できます。その知識をもとに、自分の子どもが家庭学習を得意としているかどうかを判断した上で、上手に家庭学習を習慣化させることができるでしょう。
子どもの家庭学習に興味を持っている保護者の方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
子どもにとって家庭学習が大切な理由
家庭学習とは、宿題を含む家庭での自主学習のことで、読み書きや計算などの基礎学習能力の向上を目的として行われます。家庭学習のメリットとしては以下の点が挙げられるでしょう。
・日常生活でできることが増える
・将来やりたいことの選択肢を増やせる可能性がある
・人の役に立つスキルが身に付きやすい
・知識を増やすことで趣味に活用できるなど、楽しみが増える
家庭学習によって勉強する習慣が身に付いたり、時間に縛られずに自分のペースで勉強したりすることが可能です。そうすると勉強の内容を自分で理解できるまで学べるため、日常生活や趣味に活用しやすくなります。
このように日常生活を充実させやすい・子どもの将来の可能性を広げるなどの観点から、家庭学習は子どもにとって重要です。
小学生におすすめの家庭学習方法
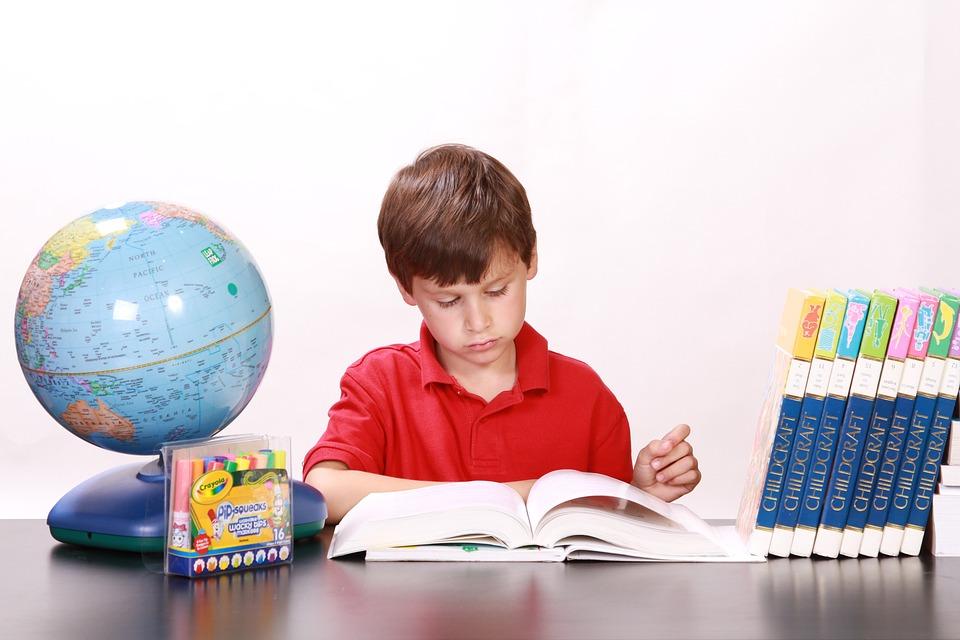
小学生で家庭学習をやっていくためには、保護者がある程度、環境を整えてあげる必要があります。また子どもの自主性を促すようにサポートするなど、子どもと協力していくことでモチベーションを上げる努力も必要です。
ここからは、小学生におすすめの家庭学習方法のポイントを紹介します。
疑問を解決できる環境や道具を用意する
家庭学習をするなかで、解けない問題が出てきた時にすぐ解決できないと、集中力が途切れてしまう可能性があります。
このため、疑問が出てきた時にすぐに解決できる教科書や参考書、学習アプリなど解決するための道具を手が届くところに用意することがおすすめです。
それでも疑問が解決できなかった時のために、保護者が近くにいる場所(リビングなど)で勉強するなど環境を整えることも推奨されています。
ただリビングの場合は、テレビなど集中力が途切れてしまうものが近くにあることも多いため、注意が必要です。
子どもに学習のスケジュールを作ってもらう
家庭学習は自分たちである程度自由にスケジュールを決められるため、まずは継続しやすい学習スケジュール(学習計画)を作ることが習慣化させる意味でも効果的です。
注意点として、学習スケジュールは保護者ではなく子どもに作ってもらうようにしましょう。保護者が決めると「やらされている」という意識からモチベーションが下がりやすいため、あくまで保護者はアドバイスなどに徹することが必要です。
目標を決める
家庭学習の意味が理解できない場合のおすすめの学習方法が、ゴールや目標の設定です。これはあくまでも短期的なものとして考え、高い目標を決める必要はありません。
「成績を〇〇あげる」や「テストで〇〇点取る」など、目でみてわかりやすい目標を設定すれば、勉強のメリハリがついてモチベーションも維持しやすくなります。慣れてくれば、長期的な目標を設定するのもいいでしょう。
規則正しい生活をおくるようにする
文部科学省の平成18年度のデータによると、子どもの基本的な生活習慣の乱れがみられるようになっており、学習意欲や体力・気力の低下に関連しているとしています。
実際に毎日朝食をしっかり食べている子どもの方が、食べていない子どもと比較するとペーパーテストの得点が高い傾向にあるというデータもあります。
このことから、食事・運動・睡眠など基本的な生活習慣を守り、規則正しい生活をおくるようにすることが大切です。
学習方法を決めておく
小学生の学習方法は、学年ごとにポイントや方法が異なります。低学年の場合は、まず勉強する習慣を身に付けさせることからはじめ、中学年では基礎力を身に付ける勉強、高学年になってからは復習していく勉強がおすすめです。
そしてどの学年でも共通しているのは、最初に宿題をきちんとやらせることです。宿題は机に向かう習慣を身に付けられるほか、勉強のやり方を覚えるという効果も期待できます。
その点を踏まえて学習方法を決める時には、自己動機づけ方略を意識させることもおすすめです。これは、学習に向けて自らの意欲を高めるために使う方略で、遊びと勉強のメリハリをつけることができる効果的な方法となっています。
やり方としては、遊ぶ時は遊んで勉強する時は集中するなど、学習時間に区切りをつける方法が一般的です。ほかにも勉強する環境を整える、ご褒美のために勉強するなど、勉強する理由に自分なりに動機をつける方法が用いられています。
自己動機づけ方略を用いることで、自分はここまでできるという意欲を高められるほか、学習への意欲の維持向上につなげられるという効果があります。
具体的な学習方法の決め方としては、たとえば「comotto」で、実際の体験やデジタルツールを活用してみるのもおすすめです。
小学校低学年向け「comotto」のサービスでは、お金のまなびや自然・環境のまなび、などの教育が利用できます。
小学校高学年「comotto」も同じような内容をまなぶことができますが、さらに深掘りした内容を学べる商材が揃っているところが魅力です。
間違えた部分を書き留めるノートを作っておく
問題を解いている時に間違えてしまった場合には、間違えた部分を書き留める「間違いノート」または「問題復習ノート」を作成する方法があります。
間違えた部分を書き留めることで、なぜ間違えてしまったのか分析できるため、自分の弱点を見つけたり、間違えた原因を解消したりできるでしょう。
このように間違えた部分を書き留めれば、間違いは大切な気づきだと前向きに捉えやすくなり、成績アップや勉強への意欲を高めることができます。
子どもに学習内容を説明してもらう
家庭学習で勉強した内容を子どもから直接説明してもらうことで、子どもにとって勉強できたという自信につながります。また言葉で説明できるということは、学習した内容をきちんと理解できている証明でもあります。
ほかにも学習内容を言葉で説明することで記憶として定着するなど、学習能力の向上に役立つ方法としておすすめです。
好きな教科から勉強する
いきなり苦手な教科から学習しようとしても、苦手意識が強くなってモチベーションが下がってしまう可能性があります。
そこから勉強を嫌いになってしまう場合もあるため、学習習慣が身に付くまでは、好きな教科や得意な教科から勉強することがおすすめです。
好きな教科や得意な教科がない場合は、解ける問題から取組んでもらうようにする方法もあります。
読書や辞書引きを習慣にする
家庭学習で宿題以外に何をさせたらいいかわからないという場合は、興味のある分野の読書をしてもらうのもひとつの学習方法です。本を読むことで語彙力や読解力を身につけることができるなど、国語の力を養えます。
また、わからないことや気になることがあった場合に辞書を引く習慣も身につけておけば、勉強になるだけではなく、学習意欲を向上させられるでしょう。
小学生が家庭学習を習慣化させるコツ
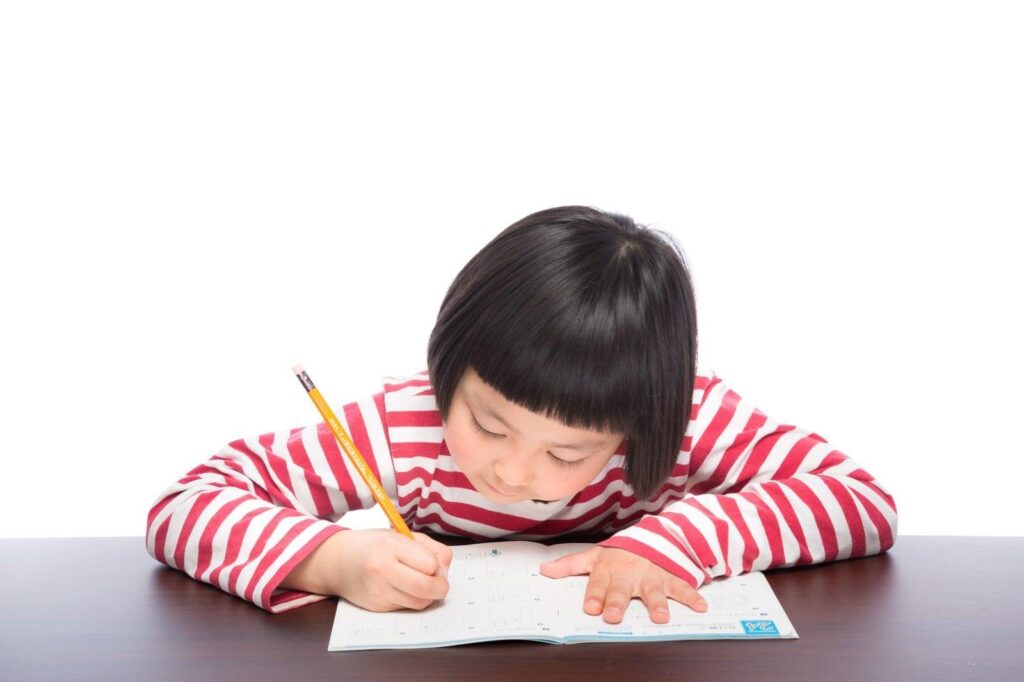
小学生のうちから家庭学習を習慣化させることで、保護者が声をかけなくても自然と取組めるようになります。ただ家庭学習を習慣化させるためには、子どもが勉強に対してやる気やモチベーションが続くように環境を作ることが大切です。
ここからは、小学生が家庭学習を習慣化させるコツを2つ紹介します。
・保護者が学んでいる姿勢を見せる
・子どもがイライラしていたら声かけをする
保護者が学んでいる姿勢を見せる
子どもだけではなく保護者も勉強することで、その姿にならって勉強してみようという意欲を引き出しやすくなります。そのため、まずは保護者が率先して学んでいる姿勢を見せることが大切です。
逆にいえば、子どもが勉強していないからと叱りつけるだけ、または子どもが勉強しているそばで保護者がスマートフォンやタブレットで遊んでいると、「なぜ自分だけ勉強しているのか」とモチベーションが下がりやすくなります。
子どもがイライラしていたら声かけをする
家庭学習をしていると、なかなか解けない問題が出てくるなど、子どもがイライラしてモチベーションの維持が難しくなる場合があります。このような場合、保護者は「何かあったの?」や「どうしたの?」と優しく声かけをすることがポイントです。
その上で子どもの話をしっかり聞いて、子どもがイライラしていることに対して共感するような声かけをします。さらに、なぜ問題が解けないのか一緒に考える、問題を解くサポートをするなどの対応も大切です。
家庭学習が苦手な子どもの特徴
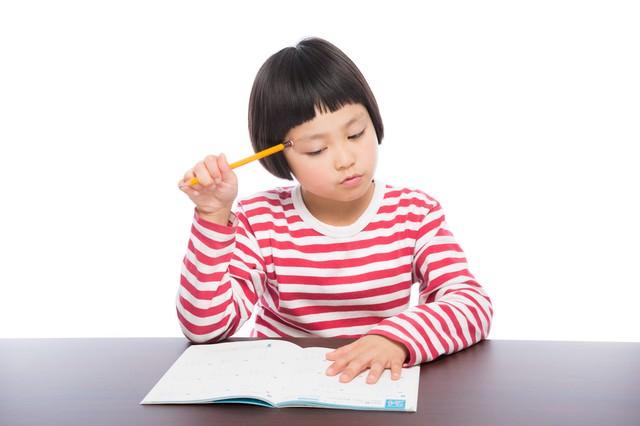
小学生のなかには家庭学習が苦手だという子もいますが、保護者として、なぜ家庭学習を苦手としているのか理由や原因を把握しておく必要があります。
また、家庭学習が苦手と感じる小学生には、いくつか共通する特徴があるため、自分の子どもが当てはまるのかチェックしてみることも大切です。
ここからは、家庭学習が苦手な子どもの特徴や原因を解説します。
・勉強できる環境がない
・体力が足りていない
・生活時間が不規則である
・勉強のやり方がわからない
・周りの友人と比べてしまう
・勉強する目的がわからない
・集中力がない
勉強できる環境がない
家庭学習に集中するためには、勉強できる環境が整っていることが必要です。勉強できる環境とは、遊びなど誘惑するものがない・静かで勉強に集中しやすい環境のことをいいます。
たとえば勉強できる静かな環境がない場合や、勉強できる部屋はあってもゲームやスマートフォン、漫画などが置かれていて集中できない場合は、勉強できる環境とはいえないでしょう。
リビングなど家族が集まる場所が勉強場所となっている子どもは、ほかの兄弟や家族がにぎやかで集中できないという場合もあるため、注意が必要です。
体力が足りていない
文部科学省のデータによると、生活習慣の乱れが起きると体調に悪影響が出やすくなっており、基礎体力が低下して学びへの意欲低下・物事への興味関心が薄れてしまうことがわかっています。
このことから、生活習慣が乱れて体力が足りなくなっている子どもは、家庭学習をしても集中できず、まなぶことができなくなってしまうと考えられています。
ほかにも何らかの理由で体が疲れてしまっている場合も、勉強するための体力が足りなくなっているため、同じようなことがいえます。
生活時間が不規則である
睡眠時間や食事時間など生活に関する時間が不規則になってくると、学習意欲を低下させるだけではなく、気力も低下させる要因になってきます。
このため、普段から生活時間が不規則になっている子どもは学習意欲が下がっているため、家庭学習をさせても集中できない傾向がみられやすいです。
勉強のやり方がわからない
学習や勉強に慣れていない子どもや苦手意識を持っている子どもは、そもそも、どうやって勉強すればいいのかわからない場合があります。
このような場合は、保護者や教師、クラスメイトからアドバイスをもらったり手伝ってもらったりするなど、日々の積み重ねで勉強方法や学習方法を覚えていくことが大切です。
また、自分に合った勉強方法がわからずに、勉強へのモチベーションが上がらないから苦手だと感じている子どももいます。
周りの友人と比べてしまう
小学生はクラスメイトや友人からの影響を受けやすく、学力や家庭環境などさまざまな要素を周囲と比べてしまう傾向があります。その結果、周りの友人と勉強方針などを比較し、家庭学習を苦手に感じてしまうことも少なくないでしょう。
ほかの友人が家庭学習をしていない場合は、どうして自分ばかり勉強しなければいけないのかと保護者との関係が悪くなる可能性も出てきます。
このように習熟度の仕方を比べて落ち込む、自分がどんなに勉強しても友人には勝てないのだから仕方ないなど、ネガティブな気持ちから家庭学習のモチベーションが下がってしまうこともあります。
勉強する目的がわからない
そもそも、なぜ家庭学習をしなければいけないのか、勉強しなければいけないのか、その理由や目的を子どもが理解していないと、家庭学習に苦手意識を持ってしまいます。
理由や目的のわからないものには取組む意欲そのものが起きないので、興味や関心を持ってくれる可能性も低いです。
このため、ただ苦痛でしかない勉強や学習よりも、友人との遊びや娯楽の方に走ってしまう傾向があります。
集中力がない
文部科学省が開催する政策・審議会では、近年の幼児の育ちには、さまざまな課題があるとされており、小学校1年生のクラスでの集中力のなさによる学習意欲の低下や学級の機能不全が指摘されています。
また体力が十分に備わっていないなど、家庭学習が苦手な子どもの特徴に関連した集中力のなさも、家庭学習を苦手としている要因となっているところも問題でしょう。
この集中力の欠如に関しては、そもそも勉強への苦手意識が強いことや家庭内でのゲームやスマートフォンなどの誘惑が多い・誘惑に勝てないことも原因となっています。
小学生の望ましい家庭学習時間は「学年×10分」
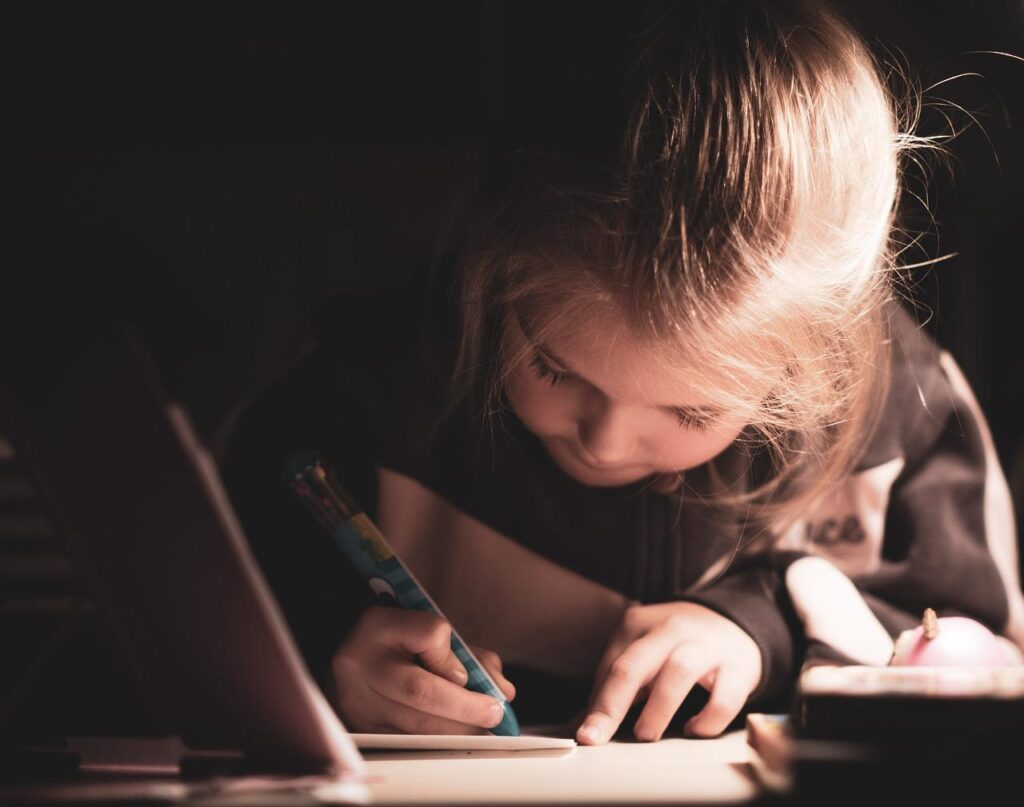
家庭学習の時間はある程度時間を取る必要があり、学年によって望ましい家庭学習の時間は異なります。一般的には、「学年×10分」を目安に時間を確保することが望ましいという見解が多いです。
東京都福生市では、「ふっさっ子スタンダード」という学習や生活の統一基準を設けており、「学年×10分」を目安に掲げています。
この目安の背景として、「福生の子どもたちの家庭学習と平均正答率」のデータを見ると、1時間以上家庭学習をしている小学校6年生の平均正答率が、74.6%から82.5%と高い結果が出ています。
このことからも、「学年×10分」を目安とした家庭学習の時間を確保することが望ましいと考えられています。ただこれはあくまでも目安となるため、子どもの学年や家庭学習への慣れ、集中力を踏まえて時間を設定することが大切です。
出典:家庭での働きかけで学力アップを|福生市教育委員会
家庭学習を習慣づける方法を知っておこう
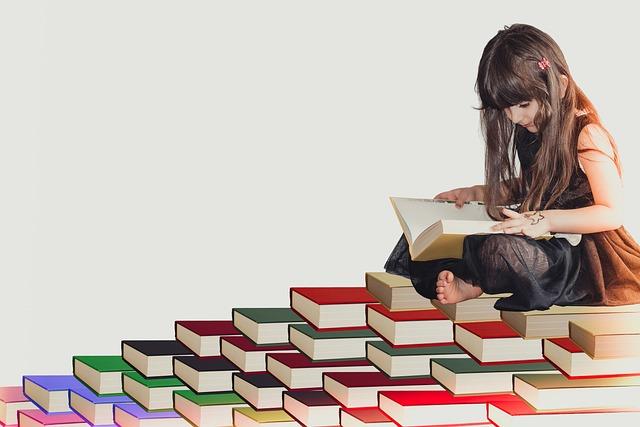
小学生などの小さい子どもは、家庭学習をはじめとした勉強や、宿題の目的や意味がわからない場合があります。さらに、ゲームなどの誘惑に負けずに自分たちで積極的に取組むことは難しいでしょう。
このため保護者は、家庭学習の大切さや目的をしっかりと子どもに伝える努力が必要となります。そして勉強できる環境づくりやサポートなど、子どもが家庭学習を習慣化できるように支援していかなければいけません。
家庭学習が苦手な子どもに悩んでいるという人は、この記事を参考に子どもが家庭学習に取組めるように一緒に頑張ってみてはいかがでしょうか。
