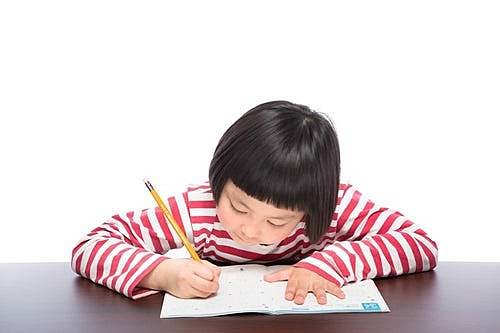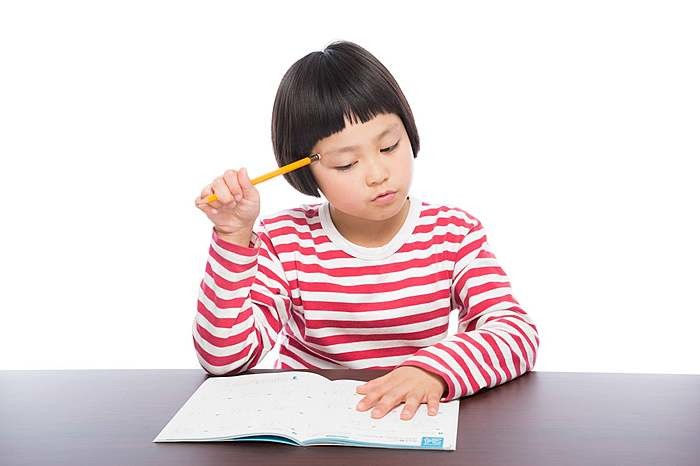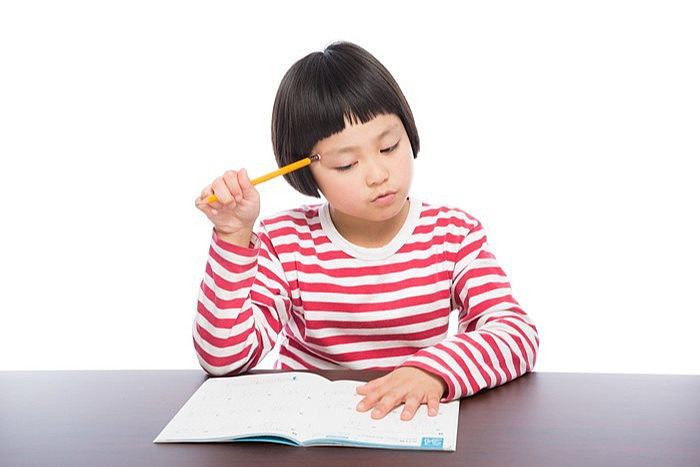高校生の読書感想文はこれで完璧!書き方と本の選び方を詳しく解説
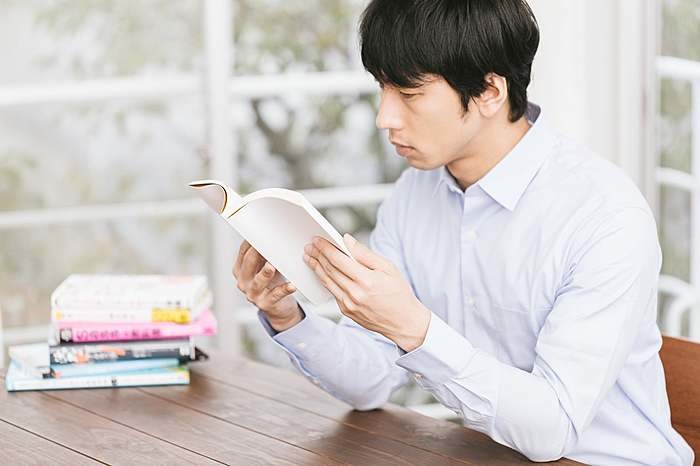
高校生の読書感想文の課題に苦戦している、という方もいるのではないでしょうか。本記事では、読書感想文に書くべき内容、本を読むときのコツ、優秀な読書感想文を書くためのポイントなどを紹介しています。読書感想文を書くときは、ぜひ参考にしてください。
「高校生の読書感想文は何を書けばよいの?」
「高校で読書感想文の課題が出たけど、本が決まらない」
「子どもにアドバスを求められたときに、きちんと答えられるようしたい」
このように高校生の読書感想文で悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、高校生の読書感想文で書くべき内容、本を読むときのコツ、書くときのポイント、親ができるアドバイスなどを詳しく解説しています。記事を読むことで、読書感想文の書き方のコツをつかみ、スムーズに書き進めることができるでしょう。
読書感想文の課題が出たときに、スムーズに終わらせられるよう事前にポイントを把握しておきましょう。
読書感想文の書き方・本の選び方に悩んでいる方は、ぜひ最後まで記事をチェックしてみてください。
高校生が読書感想文に書くべき内容
読書感想文は、高校生にとって国語力や思考力を高めるためによい方法であり、優れた読書感想文を書き上げるためには、いくつかの要素が求められます。
生徒は単なる感想だけでなく、深い洞察や知識を表現し、独自の視点から本に向き合うことができるでしょう。
ここでは、読書感想文に書くべき内容をご紹介します。ポイントを押さえることで、優れた読書感想文を書くことができるようになるでしょう。
本を読んで得た知識・感想
書いてある内容をそのままコピーしたり、あらすじをまとめるだけでは、よい評価を得られません。読書感想文で重要なのは、本を読んでどんな知識を得たのか、どんなことを感じたのかを書くことです。
具体的には、なぜその本を選んだのか、本を読む前後で自身の考え方に変化はあったか、その本を読んで印象に残った部分はどこかなどを書きましょう。
本を読んで考えた自分の意見
本を読んだ感想に加え、書かれていることに対して自分が考えた意見も書けるとよいでしょう。具体的な感想を書いたあとに、なぜそのように考えたのかを書き加えることで、読書感想文の読み手にも内容が理解しやすいものになります。
たとえば、「主人公がどんな状況でも突き進む姿に感銘を受けたのは、自分も日頃の生活で見習いたい姿勢だと思ったからだ。」のように書くとよいでしょう。
主題やテーマを掘り下げる
読書感想文を書くときは、選んだテーマを深く掘り下げて感想を書くことを意識しましょう。
著者が本を通して伝えたいメッセージは何か、読者に本を読んでどうなってほしいのか、などを探求することで、内容の濃い読書感想文を書くことができます。
また掘り下げた内容を自身の経験や、現実での例と結びつけて書き進めるのもおすすめです。
本を読むときのコツはメモをとること!

ただ本を読み進めるだけでは、読み終わっても内容が頭に残らない場合があります。細かい内容を把握できず、あとから気になる箇所を探したりすると時間もかかるでしょう。
読書感想文を書くときには、本を読んでいる途中で感じたことや気になることがあれば、読み進めるのをいったん止め、メモを取ってください。ただ付箋を貼るだけでなく、何で気になったのか、読んだときにどう感じたのかも併せて書いておきましょう。
【書き方】高校生は四段落構成を意識しよう

読書感想文を書くときに、やみくもに書き出してしまうと、まとまりがなくなり読みづらい文章になってしまいます。自分の考えを正しく読み手に伝えるためにも、まず全体の見通しを立ててください。
書き方は、4段構成を意識して書くようにしましょう。事前に、各構成ごとに何を書くのか考えておくと、スムーズに書き進めることができます。ここでは、各構成で書くべきことをご紹介します。
第一段落『書き出し』
書き出しでは、全体で約10分の1の文量を目安に書きます。優れている読書感想文を書くためには、書き出しで読み手を一気に文章に引き込めるかどうかがポイントです。
本文の引用や自分が感じたこと、本を選んだ理由などを書いてみましょう。具体的な書き方は、「学校に立ち寄った本屋さんで、表紙を見て一気に引き込まれました。購入し読んでみると〇〇に気づくことができました。」などです。
第二段落『要約』
第二段落では、本の内容を要約し、主題やテーマを明確に示すことが重要です。目安としては全体で約10分の1の文量で書きましょう。
ここでは、本の内容をざっくりまとめるだけでよいため、長々と本の紹介をしてしまわないように注意が必要です。もし書きすぎた場合は、読み返して不要だと感じた箇所をカットしてください。
要約の書き方としては、「〇〇(本の名称)は、△△な物語です。〇〇な部分が非常に印象的だった」のように書いてみましょう。
第三段落『感想』
感想は読書感想文の大部分を占める、重要な構成要素です。全体で約10分の6の文量を目安に書きましょう。
感想を書くときは、本を読んでいるときに残したメモを活用しましょう。本を読んでいて気になった部分、そのときに感じたことなど、自分の気持ちを書きます。すべてのメモを文章に書こうとせず、特に印象に残った場面に絞って書くのがおすすめです。
具体的な感想の書き方は、「私は〇〇の部分を読んだときに、△△のように感じました。なぜなら以前から私も、××のように感じており、共感できる部分が多かったからです」などを参考にしてください。
第四段落『まとめ』
最後に読書感想文全体をまとめます。文量は約10分の2を目安に書きましょう。本を読んで学んだこと、読む前後での気持ちの変化、本を読んで得た知識を今後どのように活かしていくのかを書くのがおすすめです。
具体的なまとめの書き方は、「私は本を読む前、〇〇について△△のように考えていました。しかし、本を読んで××の考え方もあることに気づかされました。今後はこの本で学んだ○○な視点・考え方を持って、過ごしていきたいと思います」のように書くとよいでしょう。
高校生が優秀な読書感想文を書くためには

高校生が優れた読書感想文を書くためには、ほかの文献を引用したり、読み手にわかりやすく題名や本文を工夫することが求められます。
ここでは、高い評価を得られる読書感想文を書くためのポイントをご紹介します。優れた読書感想文を書きたい方は、ぜひ、参考にしてみてください。
ほかの文献を引用しよう
優れた読書感想文にするために、ほかの文献を積極的に引用しましょう。ほかの本や論文、新聞などを引用することで、自分の意見を裏付けつつ、深い内容を執筆できます。意見した上で自分の考えを書くことができるので、厚みのある文章を書けるでしょう。
本を読んで感じたことを書く際も、引用や具体的な証拠を残すよう心がけてください。読み手にとっても、書き手がどこから情報を得てきたのかを確認することができます。
タイトルはわかりやすく作ろう
読書感想文のタイトルは、わかりやすく簡潔にしましょう。高校生だからという理由で難しいタイトルを付ける必要はありません。読み手がわかりやすいかつ、興味を引けるようなタイトルがよいです。
具体的には、「〇〇を読んで」「〇〇を読む前とあと」「〇〇を読んで私は△△になった」などを参考に考えてみましょう。
自分の変化について書いてみよう
本を読む前とあとで自分の変化や、本に対する印象をまとめることは重要です。具体的な気持ちの変化や考え方の転換に焦点をあてながら、読者に感動や洞察を伝えられるようにしましょう。
具体的な書き方は、「この本を読む前とあとでは、○○のように考え方が変わりました。」「これから私は、○○のようにしたいと思います。」などです。
読書感想文が書きやすい本の選び方

読書感想文を書くためには、自分にとって書きやすい本を選ぶことがポイントです。書きやすい本であれば、興味関心を持って読み進められたり、高いモチベーションで書けたりできます。
ここでは、読書感想文が書きやすくなる本の選び方についてご紹介します。
高校生の課題図書から選ぼう
読書感想文を書くための本が、なかなか決まらないという高校生の方もいるのではないでしょうか。そのような高校生には、「青少年読書感想文全国コンクール」が指定している、課題図書がおすすめです。
これらの課題図書は内容が年齢に合ったものが選ばれているため、高校生でもスムーズに書き進めることができるでしょう。
自分と関わりのある本を選ぼう
個人的な共感や経験が得られる本を選ぶことも重要です。自分が今までに経験したり、普段考えていることに共通した本を選んでみてください。
たとえば主人公と同じスポーツをしている、趣味が共通する、境遇が似ているなど自分と重なる部分がある本を選ぶことで、読書感想文をより深く書くことができるでしょう。
「名作」を読んでみよう
普段あまり本を読まないという方は、一般的に名作といわれるような本を選んでみるのもおすすめです。名作は世代を超えて愛されている作品なので、高校生でも楽しく読むことができるでしょう。
長年にわたって知られているのには、それだけの理由があり、その理由を紐解くために読んでみるのも面白いです。また本を読むことで、自身の教養力アップにもつながります。
読書が苦手なら短編集を選ぼう
読書が苦手という方は、短編集の読書感想文を書いてみましょう。短編集であれば、1つのエピソードも把握しやすく、苦手意識を克服しやすいです。
「本のジャンルは何でもよい」と考えることで気楽になり、自分が面白いと感じられる本と巡り合える確率も高まります。
子どもにアドバイスを求められたら

読書感想文の書き方について、子どもにアドバイスを求められたら、きちんと答えてあげられるでしょうか。質問されたときに備えて、読書感想文を書くときに送るアドバイスの仕方を把握しておきましょう。
ここでは、高校生の子どもに親からできるアドバイスをご紹介します。
「細分化」を意識するようアドバイスしよう
読書感想文を書くときは、「細分化」を意識するように伝えてみましょう。本の感想を文章に起こすためには、言語化が必要です。言語化するにあたり、重要なのは語彙力ではなく、細分化になります。
ざっくりとした感想を書くのではなく、自分は何を持ったのか、なぜそう感じたのか、そう感じた理由のように深堀と細分化を行って文章にまとめてください。上手く細分化が進まないときは、「具体的にどう感じたの?」と声をかけてあげましょう。
自分のおすすめの本を紹介する
子どもが読書感想文の本選びに悩んでいたら、親が自身の読書経験からおすすめの本を紹介してみましょう。高校生の頃に読んでいた本や、最近気になっている本の話をするのがおすすめです。
親が本の魅力や影響を語り、子どもに新しい読書の世界を広げる手助けとなります。親子のコミュニケーションの一環として、共感と理解を深めましょう。
褒められる読書感想文を目指そう!

ここまで高校生の読書感想文の書き方、本を読むときのコツ、感想文の書き方のコツなどを詳しく紹介してきました。
優れた読書感想文を書くためには、事前にポイントを押さえ、それを着実に実践することが求められます。本記事を参考に、読書感想文を書きあげましょう。